
世界のeスポーツの市場規模は現在約700億円、オーディエンスは2020年には約5億人に達すると予想され、大きなビジネスチャンスがあることは間違いない。国際オリンピック委員会(IOC)は2017年、eスポーツが「スポーツ活動として考えられる可能性がある」と表明し、五輪競技種目に採用する可能性を模索。2018年7月には、「eスポーツ」と五輪運動の未来をテーマにしたフォーラムを開催した。
国内でも、競技団体「日本eスポーツ連合(JeSU)」が2月に設立されるなど、2018年は“eスポーツ元年”と謳われるほどの活況を見せている。
しかし、ゲーム産業の最先進国でありながら、日本におけるeスポーツやその競技者の地位は悲惨なまでに低い。法整備から国民の意識変容まで、立ちふさがる課題を海外の現状から考える。
似ているようでまるで違う日本とアメリカの「ゲーム文化」。その岐路は90年代にあった
「日本人にとってのゲーム」と海外のそれは、いったいどう「違う」のか。立命館大学ゲーム研究センター・立命館大学映像学部に所属し、国際経営・コンテンツ産業論専門の中村彰憲教授は次のように語る。
「アメリカで競技としてのゲームの歴史が始まったのは1970年代中頃です。米ゲーム大手だったAtari社主催のゲーム大会が行われたり、日本のメーカーである任天堂が大会を主催したりもしました。
一方日本でも、1979年に始まった『ゲームセンターあらし』というコミック・アニメ作品で『大きなモニターでたくさんの観客のもとゲームで戦う』というコンセプトがすでに提示されており、80年代における高橋名人の登場など、ゲームが社会現象になるようなムーブメントも起こっていました。
とはいえ、90年代までは両国ともにソフトや施設のプロモーション的大会が多く、ゲーム大会の目的は『ゲーム企業の収益の最大化』でしかありませんでした」
つまり、90年代初頭の段階では、日米のゲーム競技の発達はほぼ“パラレル”だったのだ。ところがそれ以降、その道は大きく乖離していくことになる。
「アメリカでは家庭用ゲームではなく、PCによるネットワークゲームカルチャーがゲーム競技の主流になっていきました。そこにあったのはインターネットで繋がったユーザー同士のコミュニケーションです。これまでメーカーが主催していたゲーム大会が、ユーザー主導となったのです。ユーザー主導となることで起こったのは、『どうやってトッププレイヤーを選ぶか』『どうコミュニティを盛り上げるか』という、極めてスポーツ的な視点でした」
ゲーム競技の主体が完全に逆転し、ユーザー主導となったアメリカでは、twich.tvなどゲーム大会を放映するメディアが続々と立ち上がり、NBAをはじめとしたプロスポーツ団体がeスポーツチームを結成するなど、大会の大規模化が進んでいく。賞金や集客も完全にビジネスモデル化され、現在ではeスポーツのエコシステムが確立している。
ゲームに対する純粋な“パッション”で動く日本のゲームユーザー
一方の日本はどうだったか。実は90年代以降のアプローチが、現在eスポーツが“イマイチ受け入れられていない”現状にも繋がるのだという。
「日本のゲーム産業が非常に強いのは、皆さまもご存じの通りです。一方でeスポーツ業界は弱い。これはアブノーマルな状況だと言えます。
ASEANの国々を見ると、賞金獲得者『数』は日本の方がマレーシアやフィリピンよりも多いですが、賞金『総額』ではマレーシアやフィリピンが日本よりも大きい。日本では法律の問題もあり高額賞金の大会が少なかったのですが、理由はそれだけではありません。日本のプレイヤーには“賞金目当て”でゲームをプレイするという感覚がほとんどないのです。
では何が目的か。私は『パッション』だと思っています。ゲームに対する純粋な気持ちや愛情が、プレイヤーを動かしてきたんですね」
そこにあるのはゲーム産業大国だからこその「ゲーム愛」なのか、日本人の国民性なのか。そのアプローチは卑下するものではないが、ユーザー主導で価値を捻り出し、ビジネスモデルに変えていくという視点は持たなかった。
現在、いわば“逆輸入”する形でアメリカ型のeスポーツが導入されてもすんなりと受け入れられない原点には、大会の主体が違うことに加え、ゲームとの向き合い方にもありそうだ。
立ち塞がる「法の壁」 日本で高額賞金の大会は開催されるか
一方、日本でプレイヤー主導での大会が大規模にならなかった理由は法律にもある。著作権法上、草の根のゲーム大会は「非営利かつ無料」であれば許されるが、参加費が発生すれば許されない。営利性がなくては、大規模な大会は望むべくもなかった。であれば、行政や業界が主体となって、エコシステムを整備していくほかない。
次に“賞金”に目を向けてみよう。賞金総額が極めて低い日本のeスポーツ。金額の低さはプロゲーマー誕生の障壁となり、eスポーツ振興のブレーキともなっている。今後、日本のeスポーツにおいて、賞金の高額化は可能なのか。立命館大学ゲーム研究センター・立命館大学法学部に所属し、知的財産法専門の宮脇正晴教授は次のように話す。
「まず、景品表示法(以下、景表法)が絡んできます。『ゲーム大会』では最高でも10万円以上の景品は認められません。なぜかというと、ゲーム大会では、種目となっているゲームのユーザーになる、つまりゲームを買わないと参加(プレイ)できないわけです。従来のスポーツでは例えば『ミズノのグローブを買わないと野球大会に参加できない』なんてことはありません。ですから、景表法の範疇になってしまうんですね。
一方、ゲームを生業としている『トッププレイヤーたちのプレイ』であれば、仕事として認められるため景表法に引っかかりません」
2018年になってようやく競技団体「日本eスポーツ連合」が設立された日本。大会規模と賞金金額の拡大のために、法整備を含めた行政への働きかけも必要不可欠になる。
鬼ごっこよりもスポーツらしくない? 「スポーツ」という言葉が持つ先入観
現在、eスポーツ賞金総額でトップに立つのが中国である。中国では2002年に日本の総務省に当たる信息産業省が大会を開催するなど、行政が強くバックアップしてきた。民間主導のアメリカとは真逆のアプローチだが、今ではビジネスモデルとして成立している。
「あらゆるスポーツは必ず、国や社会の認知・需要を経て成長していきます。中国や韓国のように、国が協力して認知を広げていかないと、ゲームを産業として、さらにはeスポーツとして発展させることは難しいでしょう。
フィリピンではeスポーツアスリートライセンスを国が発行し、所有者はアメリカの大会に参加するためのビザを得ることができます。ドイツでは2018年からeスポーツを正式なスポーツと国が認めました。海外の状況と比しても、日本は遅れていると言わざるを得ません」(中村教授)
ある調査では、「eスポーツは実際に身体を動かすことがメインではないので、スポーツ競技とはとらえにくい」と思う人が20%に達するという結果もある。中には「鬼ごっこよりもスポーツらしくない」というコメントも見られたほどだ。
今後、日本人の根底にあるこの「先入観」を、どのように払拭していけばいいのだろうか?
「eスポーツプレイヤーの知能的なすごさを正しく伝えることが重要です。反射神経や戦略性、先読みや駆け引きのテクニック。世界の強豪に勝つ“すごさ”をいかに伝えていくか。その試行錯誤が必要になるでしょう」(中村教授)
日本にはゲームのノウハウの蓄積も歴史もある。ソフトウェアも、トッププレイヤーも存在する。つまり、「材料は全てある」のである。それを未来に繋げていくために必要なのは、私たちのゲーム、そしてeスポーツに対する意識変容なのだ。
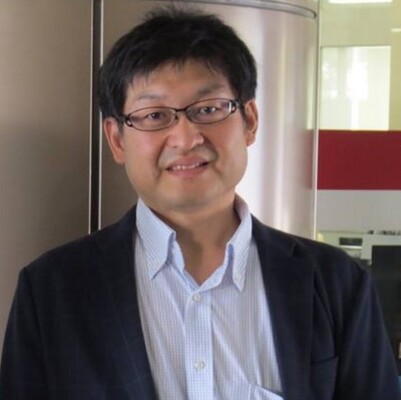
中村彰憲
名古屋大学大学院国際開発研究科修了。博士(学術)。早稲田大学アジア太平洋研究センター、立命館大学政策科学部助教授を経て、映像学部映像学科教授を務める。主な著書に『中国ゲーム産業史』(Gzブレイン)など多数。その他、ゲームビジネス全般に関するコラムを定期的に寄稿している。




















