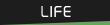対人関係の悩み、精神疾患、いじめ、貧困…。さまざまな要因から「生きづらい」と感じる若者の存在が浮き彫りになっている。コミュニケーション方法や労働環境、家族の在り方などが急激に変化する中で、社会は「生きづらさ」を増しているのだろうか? 社会学の視点で俯瞰するとき、そこにはこれまで「中間集団」が果たしてきた役割の大きさが浮かび上がる。
● 生きづらさを抱える人は「中間集団」に帰属していない?
● 私たちの帰属する中間集団とは?
● 強制力と他世代性が、中間集団をつくってきた
● コロナ禍が加速した個人化
● 未来の中間集団を「つくりだす」必要がある
「生きづらい」と感じる人が喪失しているかもしれない「中間集団」とは
立命館大学 産業社会学部の景井充教授は、滋賀県大津市の「大津市子ども・若者支援地域協議会」の会長を務め、「引きこもりや家族に問題を抱える当事者」をサポートする行政担当者の研修などに取り組んできた。
一方、専門である社会学の見地からこのような「生きづらさ」を見つめたとき、景井教授はあるものの欠如、あるいは彼らが「手に入れられていないもの」に気付かされたという。
「引きこもりの事例などをみていると、当事者の深くて重い孤立に圧倒されます。では、その孤立の背景に何があるのか。社会学の知見を動員してこの事象を見ると、当事者が『中間集団』に帰属していない状態にあると捉えることができると思います。
中間集団とは、社会全体と個人との間に位置する集団のことで、家族・会社・組合といったものがわかりやすいでしょう。そういった共同体的な性格を帯びた集団に帰属していない。ズバリ、孤独なのです。」
では、我々が帰属する「中間集団」とは、具体的にはどのようなものだろうか。

「第一はやはり家族です。そして、子どもや学生なら、学校のクラスメイト(教室集団)ということになるでしょう。もう少しプライベートな枠組みもあり、例えば同じ塾の生徒仲間なども中間集団といえます。
逆に言えば子どもたちは今、成長過程の中でこのような中間集団“しか”持たないことが少なくありません。塾の形態も10年ぐらい前からどんどん個人指導にシフトし、日常生活で関わりを持つ人の数はすごく少なくなっています。小中高という12年間の生活圏が、学校と家と塾のトライアングルに閉じているんですね。
多少はみ出したところがあるとすれば、マクドナルドやゲーセンなどです。彼らにとってある種のサードプレイスですが、そこでのコミュニティには立体性がありません」
お祭りをつくり上げる強制力は「生きづらさ」を緩和していた?
子どもたちや若者は、帰属する中間集団が失われたことによって、どのような影響を受けているのだろうか。景井教授は、共同体が本来的に持つ強制力と、構成員の世代の広さを指摘する。

「中間集団の中では強制力が働きます。一番分かりやすいのは地域のお祭りでしょうか。だんじり祭りでも、三社祭でも構いません。
お祭りを企画・運営していくシーンでは、年長者の言うことはほぼ絶対でしょう。もちろんコミュニケーションがあって単なる独裁ではありませんが、『伝統を守ることで共同体を維持する』という最も重要なテーマがあり、そのために、ある程度の強制力が働く集団がつくられます。
しかもお祭りの参加者は、その地域の顔役ともいえる老人から、地域のしきたりによってはオギャーと生まれた赤ん坊まで含んだ、極めて広いものです。
年齢層の幅や地域ごとの独自ルールなど、社会的には多少非論理的なものを含んでいたとしても、その総体が中間集団を作ります。社会学の用語で少し詳しく言えば『ある目的を実現するための手段的な集団ではなく、集団を構成すること自体を目的とする意志に基づく集団(ゲマインシャフト)』がお祭りを成立させているのです。そうした利害を離れた共同体(ゲマインシャフト)的な中間集団が、個人化の趨勢の中で急速に失われつつあると感じています」
祭りに代表されるような地域コミュニティ(中間集団)が、全国各地で消滅したり、少子高齢化などで存続を危ぶまれていることはご存じの通りだ。このような集団の喪失は、若者たちの成長や人生にも大きな影響を与えてきたはずだ。
そして、昨今のコロナ禍はその流れに追い打ちをかけた側面もある。
コロナ禍の若者たちから“抜け落ちた”ものとは
コロナ禍は、ただでさえ貴重な「学校」における中間集団の構築にも大きな影を落としている。2020年度には多くの大学や学校が閉鎖状態となり、急激にオンライン授業化が進んだことも記憶に新しい。新入生が学校にも行けず、サークルで友達をつくることもできない。親元から離れ、強い孤独を感じていた学生も多かっただろう。
「勉強は、確かにオンラインでできていた面はあります。しかし、それは情報提供と修得というサイクルがかろうじて機能していただけで、日常の学生生活は消滅したわけです。
学生生活はさまざまな集団に属しながら成り立っていますが、学生1人が持つ中間集団はいずれも20〜30人くらいで構成されています。それがある期間、失われてしまった。
一方で、それで生活できないかというと、生活できてしまうんですね。コンビニがあれば、ひとまず食べ物に困ることもなく、映画や本もスマホで好きに見ることができます。『本当に個人化が徹底するとこうなるんだ』と、恐ろしく感じました。
学生に、『お金があって、やろうと思えば、1カ月誰にも会わないで暮らせるだろう』と言うと、『うんうん』という顔をしています。資本主義的市場への依存が人間関係の希薄化・個人化を深化させてきたわけですが、コロナ禍を通じてそういう状況を我々ははっきりと知ってしまった。『生物学的生存がかからない人間関係』を排除できてしまうことがわかってしまったのです。だから、中間集団は顧みられず、重要性も失われています。
しかし、学生生活も徐々に元に戻りつつあるとはいえ、その時に“得られるはずだった”中間集団を逸したということは間違いありません。学生たちは自分たちが何を『得られなかったか』がわからず、比較する機会もないから、あまり残念とは思わないでしょう。学校という強制力が働く場所からのある種の解放感を満喫している面もあるように見受けられます。
ただ、学生たちと長いこと接している教員の経験に照らすと、彼らが得られなかったものは、たぶん生涯をかけても取り戻せないのではと危惧しています」
もちろん、コロナ禍での対面コミュニケーションの激減で一時的にでも中間集団を失ったのは、彼らだけではない。さまざまな年代にそれぞれ「失ったもの」「得られなかったもの」があるのだ。それは日本全国はもちろんのこと、世界同時的に起きたことでもある。それが将来、具体的にどんな未来として現れるかはまだわからないが、その影響は甚大だというしかない。
新たな時代の中間集団を立ちあげなければならない
地域のお祭りを担う集団に代表されるような中間集団。そういった“強制力を持つ共同体”は、現代人が「面倒くさい」と感じるような人間関係も内包している。しかし一方で、人生における生きづらい瞬間を吸収してくれたり、よりかからせてくれたりする機能がある。
「そういう中間集団をつくらなければいけないのだろうと思います。個人化はさらに加速度的に進行しています。今、日本はまだ高度経済成長期の遺産で豊かさを享受しているから、それを基盤にみんな好き勝手なことができています。しかし今後、いろいろなものが老朽化していくでしょう。物理的なインフラだけでなく、制度的なインフラ、そして、関係人口という意味でのネットワークも社会的なインフラで、そこでも強固さが失われていく。
それを踏まえれば、『新たな中間集団をつくるしかない』のではないでしょうか。会社組織など既存の“擬似的な”中間集団を利用しようとしても無理で、時代状況に合わせて創造するしかありません。
3.11の後、結婚する人の数が増えたでしょう。ああいう社会を揺るがす危機感でもないと、放っておいても集団は立ち上がってこない。だから、意図的に創り出すしかないのです」
景井教授は「家父長制的・権威主義的な制度や文化とは別の、存在論的なレベルで帰属することのできる、最近の言葉でいえば“安心と安全を手に入れることのできる”中間集団をどうやってつくりだすかが重要」だと語る。
人は独りでは生きていけない。その前提には、私たちがこれまでことさらに意識する必要がなかった中間集団があったのだ。自分と、自分が帰属してきた中間集団を振り返るとき、これからの社会に必要な中間集団の形が見えてくるかもしれない。
撮影協力:カフェ山猫軒

景井充
立命館大学産業社会学部教授。専門はフランス社会学草創期の社会思想史的研究。並行して、多様な社会問題に触れながら、日本の近代化が抱えている構造的問題とその帰結そしてまた克服の方途に関心を寄せ続けている。目下の最大関心事は、急激な縮小社会化に応じて近代日本の社会システムを脱構築し、包摂的かつ持続可能な社会システムをソーシャルデザインの手法を使って構想・実現すること、である。