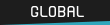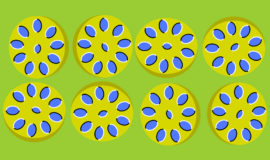アメリカ現代史には、社会と歴史を変えた女性たちの声が数多く刻まれている。その中から10人の声を拾い上げ、その背景、影響を分析したのが、5人の女性アメリカ研究者による『私たちが声を上げるとき アメリカを変えた10の問い』(2020年6月、集英社新書)だ。ここでは、大坂なおみとハウナニ=ケイ・トラスクの二人に焦点を当て、共著者のメンバーである立命館大学の坂下史子教授とハワイ大学の吉原真里教授にお話を伺った。
● 日本では正しく伝えられていない、大坂なおみ選手のアクション
● アフリカ系ハーフか? 黒人か?
● ハワイにおける「ハワイアン主権運動」とは?
● ハワイと沖縄・北海道の共通点、日本の状況に思いを馳せること
大坂が声明を出すまでの経緯を、日本のメディアはほとんど報じなかった

——『私たちが声を上げるとき』の第Ⅰ部は、#MeToo運動、ブラック・ライヴズ・マター運動が世界を揺るがした2018年から現在までの期間に声を上げた人物5人を取り上げています。その中で、坂下先生はプロテニス選手、大坂なおみのパートを担当していらっしゃいますが、なぜ彼女を人選したのでしょうか。
坂下 私が大坂なおみを取り上げたのは、若い女性、しかも常に「日本人」の境界に置かれている人物が、いざ本当に自分が訴えたいことを発した瞬間、排除されたり、バッシングされたりということがなぜ起きるのか、そこを明らかにしたいと思ったからです。
2020年8月、全米オープンテニス選手権の前哨戦にあたるウェスタン・アンド・サザン・オープンに出場中だった大坂が、準決勝前日にあたる26日の夜、自身のツイッターに英語と日本語で声明を投稿します。その声明の中で彼女は、「Before I am an athlete, I am a black woman. 私は一アスリートである前に、一人の黒人女性です」と声を上げ、「翌日は試合をしない」ことを表明しました。
このことに対し日本では、「棄権」はプロ選手として無責任だという批判が多く出されました。声明発表に至る経緯はほとんど報道されずに、です。
——大坂が声明を出すまでに、どういう経緯があったのですか。
坂下 声明発表のきっかけは、8月23日にウィスコンシン州で起きた、黒人男性が白人警官に背後から銃撃されるという警察暴力事件です。この事件で5月末以来継続していたブラック・ライヴズ・マター(BLM)運動が再拡大し、アメリカのプロスポーツ界でも、男子プロバスケットボール(NBA)や女子プロバスケットボール、プロサッカー、プロ野球メジャーリーグなどの複数のチームが予定されていた試合や練習を延期し、事件への抗議を表明していました。
大坂が準決勝戦後の記者会見で説明したところによると、準々決勝戦後にNBAの抗議行動を知り、自分も声を上げなければならないと感じたのだそうです。彼女はすぐにエージェントと電話で話し合い、その後、大会主催者の女子テニス協会(WTA)に連絡を入れます。WTAも彼女の意向に賛同し、試合の延期を決定しました。
ここまでの入念な準備を経た上で、大坂は声明を発表したのです。準決勝の対戦相手も大坂の決断を全面的に支持し、WTAは、大坂の声明発表を待ってから準決勝の延期を発表しています。
日本のメディアはこうした一連の経緯には当初ほとんど触れずに「ボイコットした」「棄権した」と報道し、その結果、無責任で身勝手な態度だという批判さえ起きました。
ちなみに、一部の海外メディアは、アスリートはそれぞれのスポーツに従事する労働者であり、自らの労働環境に影響を及ぼすアメリカの社会状況に対する異議申し立てのための行動であるとして、「棄権」や「ボイコット」という表現は使わず「ストライキ」という表現に改めています。
大坂は、日本では「アフリカ系ハーフ」アメリカでは「黒人女性」
——そうした大坂の真の姿と日本のメディアでの取り上げられ方との間のギャップは、なぜ生まれるのでしょうか。
坂下 彼女がテニスで活躍すると、できるだけ「日本人」の中に入れる感じでメディアが報道し、社会もそのように受け止めようとしている印象があります。特に、大坂が活躍し始めたころは、メディアは彼女をマスコットのように扱い、英語が第一言語の彼女に対して「新しく覚えた日本語をしゃべってみてください」とか「好きな食べ物は何ですか」とか、およそプロスポーツ選手が話す内容とはかけ離れた質問をしていました。それで彼女が面白い日本語をしゃべったりすると、それがかわいいみたいに扱われたり、そうした部分ばかりがメディアで取り上げられて、まるで子供のように扱われていることに私はとても違和感がありました。結局、日本社会の中で大坂は常に「アフリカ系ハーフ」という文脈の中に位置付けられていて、活躍すれば「日本人」に包摂されるけれど、そうでなければ「日本人」から除外されるような感じがあります。
一方、アメリカ社会の中で大坂は「黒人女性」として暮らすしかないのです。黒人の血が少しでも入っていれば黒人と見なされる「血の一滴ルール」によって、日本では「アフリカ系ハーフ」と見なされるような人々もすべて「黒人」とされ差別や迫害を受けてきた歴史を持つアメリカ社会の中で、大坂は「日本国籍」を持っていたとしても「黒人女性」の文脈の中に位置付けられてしまう。だから、彼女にとってBLM運動は決して他人事ではなかったのです。
そうした社会的、歴史的背景への理解が不十分なまま、彼女自身も自認する内向的な性格と控えめな言動によって大坂を「日本人らしい」と称賛するようなステレオタイプから抜け出せないでいるから、彼女の抗議行動の本質を捉えることができないのだと思います。

吉原 日本では、何か起きたときに、起こったことについては報道されますが、そこに至るまでの歴史的な背景や社会政治的文脈がきちんと掘り下げられないまま報道されてしまうことが多いと感じます。大坂なおみの抗議行動に関する報道は、その最たる例だったと思います。
歴史的な理解や社会的文脈にもとづいた問題意識が報道する側になければ、表象的な報道ばかりが出てきてしまう。特にアメリカの人種問題に関しては日本では一般的に理解が浅いと思うので、なおのこと表象的な報道ばかりになることを危惧しています。
坂下 声明を出す前の2020年7月、大坂は『エスクァイア』誌に寄稿し、その中で「日本はとても均質的な国なので、人種差別に立ち向かうのは難しいことでした」と語っています。大坂が声を上げたのはアメリカの人種差別に対してだけではなかったのです。彼女の問いかけを、私たちはきちんと受け止めなければなりません。
ハワイアン主権運動のリーダーは「主権とは何か」を問いかけた
——『私たちが声を上げるとき』の第Ⅱ部では、第二次世界大戦終結から20世紀の終わりまでの間の声を上げた女性5人を取り上げています。その中で吉原先生が担当なさったハウナニ=ケイ・トラスクとは、どういう人物なのですか。
吉原 ハウナニ=ケイ・トラスクは、1970年代から90年代にかけてとくに盛り上がりをみせた先住ハワイアン主権運動を牽引したリーダーです。
ハワイの名家出身のトラスクは、シカゴ大学とウィスコンシン大学で学んだ後、1977年にハワイに戻ると、海軍の砲撃演習地として使われていたカホオラヴェ島を市民の手に取り戻す運動に参加するなど、一貫して先住ハワイアンの権利回復に関わる直接行動や政府機関を相手にした活動を続けていきます。その過程でトラスクはどんどん雄弁になり、そのメッセージは先鋭化していきます。歯に衣着せぬ発言や議論を通じ、彼女は、若い学生たちをはじめとする多くのハワイアンやその運動を支持する人たちの尊敬を集め、一種のロールモデルとなっていきました。
そして、彼女の数多くの発言のうちで最も影響力を持ち歴史に残る演説が、『私たちが声を上げるとき』で取り上げた、1993年1月17日の「We are not American!(私たちはアメリカ人ではない!)」演説です。
——「We are not American!」演説で、トラスクは何を訴えたのでしょうか。
吉原 この演説は、100年前の1893年1月17日にハワイ王朝が少数のアメリカ人によって非合法に転覆させられたことへの怒りと悲しみを表し、ハワイアンの主権を主張するため4日間にわたって行われた抗議活動のクライマックスとして開かれた集会で行われました。
その集会で、1万5,000人の人々を前にトラスクが訴えかけたのは「主権(sovereignty)とは何か」という問題でした。
トラスクは、「主権とは、自らの政府を持ち、自らの国家を持つことである。自らの政府を持つことでのみ、自らの権力を行使し、自らの土地を管理することができる」「行儀良く話し合いをしている場合ではない。憤り闘わなければならない。私は憤っていることに誇りを持っている。ハワイアンであることに誇りを持っている。私は、そして私たちは、アメリカ人ではない」などと論じたのです。
トラスクの訴えが世代を超え、今、天文台建設反対運動につながっている

——トラスクの主張は、その後の先住ハワイアン主権運動にどのような影響を与えたのでしょうか。
吉原 ハワイアン主権運動が大きく、幅広いものになっていく上でトラスクが果たした役割は計り知れません。1970年代、ほとんどのハワイアンの人々が「主権」という単語を口にすることさえためらったのに対し、1990年代には世代を超えて多くの人々が運動に参加し、ハワイ社会の支配層も無視できない勢力となっていました。
どのような社会運動も、状況によって盛り上がりを見せたり、鎮まったりもします。しかし、トラスクの訴えは、確実に次の世代へと受け継がれています。
トラスクがまいたハワイアン主権の精神が見事に花開いた事例の一つが、ハワイ島マウナケア山で展開されている天文台建設反対運動です。ハワイアンにとって神聖な土地であるマウナケア山の山頂に、口径30メートル望遠鏡(TMT)の建設が進められようとしています。この巨大天文台の建設に反対する運動がハワイアン・コミュニティのリーダーたちや若い活動家たちによって粘り強く続けられていたのですが、2019年夏、土地の利用許可を有効と認める州最高裁の判決によって建設道具を山頂に運ぶ作業が始められようとすると、時には数千人規模の人が山頂への道路の入り口にテントを張って寝泊まりしながら抗議し、30人以上が逮捕される状況になっていました。
私も現地に2泊して見学してきましたが、マウナケア山の麓で続けられていたこの運動は、天文台建設反対という直接の目的をはるかに超え、ハワイアンの共同体創生の大きなうねりとなっていました。毎日3回、山や太陽などの神に祈りをささげ、フラを踊り、山を守る長老たちにささげ物をする——。ハワイアンの文化や伝統が商業的にパッケージされ、観光客向けに展示されたり表象されたりすることがごく当たり前になっている中、私が見たのは、生活の中に生きる文化として、本物の祈りとして、あるいは社会活動・政治的行為としての歌や踊りが、何千人という人によって実践されている光景でした。実際に目で見て、心を打たれました。
そして、この運動を組織していた人たちの多くが、トラスクの下で学び、さまざまな形でハワイアン主権運動に携わってきた若い世代です。
——世代を超えて引き継がれているというのは、トラスクがハワイ大学で教鞭を取っていたということも大きかったのではないでしょうか。
吉原 私はハワイ大学で仕事をしていますが、トラスクの教えを直接受けた人たちが、今、教鞭をとって教えています。
例えば、演劇学科ではハワイアンの教授の指導の下、すべてハワイ語でやる舞台を学生たちが上演しています。私も見に行ったことがありますが、何十人ものキャストがあるような作品を堂々とハワイ語で上演していることに、まず感動しました。客席もほぼ満席で、観客のかなりの人たちが、冗談を言っているらしい場面で笑うんです。つまり、そのくらいハワイ語が分かる人たちがいるということで、それにまた感動しました。
大学で、ハワイ語や、ハワイの歴史や政治・経済などを学ぶ学生たちも増えています。ハワイ大学は、まだ不十分ですがハワイアンの教員を採用するようになりましたし、ハワイアンに関する教育活動を行うことに価値を置くようになってきました。そうした流れは、トラスクの影響がすごく大きいと思います。
坂下 ハワイ語で演劇をやっているというお話を聞いて思い出したのですが、私の沖縄の友人が、例えば基地反対などを訴えてSNSで本当に言いたいことを言うときに、沖縄語というか、いわゆるウチナーグチでメッセージを書くんですね。「あとで日本語版を載せます」みたいな断りを入れて、「とりあえず、今言いたいことは第一言語で書かせてくれ」という感じで。
この本のトラスクの章を読んだ人が、すぐに沖縄のことを思い浮かべるかどうか分かりませんが、環境の問題であったり、アイヌ民族のことであったり、トラスクが告発した問題と同じような構造的な問題が実は日本社会の身近なところにもあるんだということを感じ取ってもらえるといいですね。
吉原 ハワイには、植民地化の歴史があり、軍事化の歴史があり、第二次世界大戦後は観光地化の流れがあります。植民地、軍事、観光、この3つは別々のことではなく、相互に関連しながら一つの社会経済構造をつくり上げてきたのです。その3つの歴史については、ハワイと沖縄で共通することもたくさんあります。また、沖縄からハワイへの移民も多く、つながりの深い場所と言えるでしょう。
ハワイの歴史を学んだら沖縄の歴史、さらに北海道の歴史にも思いを巡らせてみてください。北海道も、アイヌの人々が暮らす土地に開拓使やその後に移住した人々が植民したことで日本の一部となったのですから。
この本を読むことが、そうした歴史や社会的文脈を批判的に考えるヒントになれば嬉しいです。

>>(後半記事)女も男も関係ない! 「私たち」の声がモヤモヤを解きほぐす鍵になる
本書については、以下にも関連記事が掲載されているので、併せてご覧ください。
●『公研』2022年6月号「座談会」
● 毎日新聞 書籍紹介記事

坂下史子
立命館大学文学部教授。神戸女学院大学文学部を卒業後、同志社大学大学院アメリカ研究科で修士号、ミシガン州立大学大学院文芸研究科で博士号取得。専門はアメリカ研究、アフリカ系アメリカ人の歴史と文化。共編書に『よくわかるアメリカの歴史』、Transpacific Correspondence: Dispatches from Japan’s Black Studies、共著書に『「ヘイト」の時代のアメリカ史―人種・民族・国籍を考える』、 Gender and Lynching: Politics of Memoryなど。

吉原真里
ハワイ大学アメリカ研究学部教授。東京大学卒業後、ブラウン大学アメリカ研究学部で修士号、博士号取得。専門はアメリカ文化史、アメリカ=アジア関係史、ジェンダー研究、カルチュラル・スタディーズなど。日本語の著書に『アメリカの大学院で成功する方法』『ドット・コム・ラヴァーズ』『性愛英語の基礎知識』『ヴァン・クライバーン国際ピアノ・コンクール』『「アジア人」はいかにしてクラシック音楽家になったのか?』など、その他英語の著書多数。