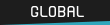今年6月、女性研究者5人が集まって1冊の本を上梓した。タイトルは『私たちが声を上げるとき アメリカを変えた10の問い』(集英社新書)。差別や不正義に対して女性が声を上げたアメリカ現代史における10の”瞬間”を取り上げ、その背景にあったものや、その後の変化などに迫っている。今回は、共著者である立命館大学の坂下史子教授とハワイ大学の吉原真里教授に、声を上げた彼女たちに気付かされたことやジェンダーの問題にどう向き合うのかなどについて語り合っていただいた。
● 女性たちが立ち向かってきた「オッサンの壁」とは
● 連帯し、互いに加筆修正をする関係性から生まれた本
● 日々の生活の中にある「モヤモヤ」を捉えること
● 著者も、読み手も、すべてのひとが「私たち」
“オッサンの壁“をよじ登ろうとした女性たち自身も、反省し始めている

——『私たちが声を上げるとき』の執筆に取り組まれる中で、新たに気付いたことはありましたか?
吉原 今の若い人たちには、むしろ私たちの方が学ぶことが多かったように感じました。日本でもそうですが、特に、この本にも出てくるエマ・(X・)ゴンザレスやZ世代の人たちは、メンタルヘルスや広義の「ケア」について非常に優れた感性を持っている。共著者の一人、三牧聖子さんも本の中でこのように書いています。
「Z世代は、メンタルの不調を語ることにオープンだ。そして、個人にメンタルのタフさを求めるのではなく、人間のメンタルに負荷をかける社会こそ変わるべきだと考える」と。
坂下 この本を書いていた昨年、東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会会長の女性蔑視発言が社会問題になりました。あのとき、すぐに「#わきまえない女」というハッシュタグが立ち、若い人たちが中心になってオンライン上で集まって緊急のトークイベントなどをやっていて、抗議文を出したり、オンライン署名を集めていました。瞬発力もあるし、組織力もある。私のようなアナログ世代にはない発信力というか、力強さを感じます。

吉原 振り返ってみれば、私たちや私たちより上の世代は、男性中心・男性優位の社会の中で何とかそこに食い込んで、同等に扱われ、ちゃんと認めてもらえるように頑張ってきた女性が多いのではないかと思います。それは、そうする必要と、そうしたいという欲求があったからです。
しかし、それでは解決しないことがたくさんあることも事実です。
昨年、全国紙で女性として初めて政治部長に就いた佐藤千矢子さんが『オッサンの壁』(講談社新書)という本を出し、その中で次のような指摘をしていました。
「オッサンの壁は登って乗り越えるものではなくて壊すものである。その壁をそのままにして、そこでよじ登っている限りでは、何とかしてよじ登れることができる女性にとっては、ある程度のところまでは到達できるかもしれないけれども、いろいろな状況によって壁にすら到達できない、あるいは登れない女性にとっては何の役にも立たないし、壁そのものは立ったままで、立ったままであるだけでなく、壁に吸い寄せられるように行く女性たちが、むしろ壁を強化することに加担することになる。別にそれを求めてやっているわけではないけど、結果的に加担することもある」
オッサンの壁をよじ登るやり方である程度のところまで来た女性が気付いて、反省し始めているのだと思います。私自身を含めて。
壁を壊すために、上に登って上から壊す人もいれば、外からガーンとやる人、壁を分析して溶かそうとする人もいます。どのやり方が正しいとか、そういうことではなくて、いろいろな方向からいろいろなやり方で壁を壊していくことが必要なのではないでしょうか。
坂下 確かに、『私たちが声を上げるとき』に登場する10人が直面した課題はそれぞれ違っていて、声を上げた方法も訴えた内容もさまざまでした。自由と平等を求め、それを阻む社会の問題を多様なやり方で問いただす、その積み重ねの先に、性別も人種も関係ない豊かな世界が実現されるのでしょう。本に出てくる10人は、そう信じていたのだと思います。
5人の研究者の共感から生まれた「シスターフッド」
——本には、声を上げた女性に共感し、連帯する女性たちも出てきます。そうした共感、連帯する人々がいて「声」も大きなものになっていくのだと思いますが、まさにこの本も、5人の「女性の連帯(シスターフッド)」から生まれたと言えるのではないでしょうか。

坂下 この本は、日頃感じている女性としてのモヤモヤだったり、ジェンダーに関しての疑問や憤りをお互いに共有して、「そうだよね、何かおかしいよね」みたいに共感し合ったところから出発しました。私たち5人が感じたことを、単に内輪で話し合って終わるのではなく、研究者として何ができるかを考えた結果、こうしたスタイルの本が出来上がったわけです。
私は本書の中で、2018年の全米オープンテニスの表彰式で、長年にわたり人種差別・性差別と闘ってきたセリーナ・ウィリアムズが新女王の大坂を支える姿は、「『白人主流のスポーツ』における人種マイノリティの女性の連帯(シスターフッド)を感じさせるものだった」と書きました。この二人の黒人女性の世代を超えた連帯に比べればとてもささやかなものではありますが、私たちも5人のシスターフッドがなければこの本は出版できなかったでしょう。
吉原 声を上げてきた女性たちが問題化してきた社会の課題を扱う本をつくるのですから、私たち自身の実践も、そうした理念や姿勢に沿ったものでなければならないと考えました。5人には年齢やキャリアにある程度幅があるのですが、ファーストネームベーシス(first-name basis)で、「真里さん」「史子さん」と呼び合ってやっていました。
坂下 この本は編者や監修者を立てていなくて、表紙の共著者5人の名前もアイウエオ順で並んでいます。本当にフラットな関係性の中で、それぞれが草稿を担当した章の内容についても互いに意見を言い合って、加筆修正をし合ってつくりました。このようなプロセス自体も、これまで経験したことのない新鮮なものでした。
誰の日々の生活の中にも「小さなフェミニズム」が紛れている

——この『私たちが声を上げるとき』を、どのように読んでほしいと思っていらっしゃいますか。
坂下 私は、フェミニズムやジェンダーの専門家ではなく、アメリカ研究が専門です。だからこそ、アメリカの特定の事例・人物を深く掘り下げて歴史や社会を分析するものを書きました。ところが、書いてみたら、結果的にフェミニズムを実践するような内容になっていました。
この本で取り上げた人たちも、ほとんどは声を上げた瞬間に「私はフェミニストだ」という意識は持っていなかったと思います。日々、普通に暮らしている中でいろいろと思う疑問や不満などがあって、あるとき「いや、ちょっとそれはおかしい」ということで声を上げた。その行為が、今から考えると結果的にフェミニズムの理論や概念で分析、説明できるような事象だったというだけなのです。つまり、誰の日々の生活の中にも「小さなフェミニズム」というか、「ジェンダーについてのモヤモヤを解きほぐす鍵」みたいなものが紛れていると思うのです。
そして、それは単に女性だけのものではないはずです。ですから誰でも気軽にこの本を手に取っていただければと思います。とても興味深い10人の話が入っているので、読んでいただいて、「大坂なおみとか、アンジェラ・デイヴィスと自分が感じていたことは一緒だったんだ」と共感するとか、「自分の奥さんが前に怒っていたのは、そういうことだったのか」と気付くとか、自分の経験に引き付けて共感してもらえるポイントが多分たくさんあります。たくさん共感し、さまざまなことに気付いて、それを自分の力にしてほしいと思っています。
吉原 この本のタイトルを「私たち〜」とした大きな理由は、著者である私たちの声を登場する10人の声にコーラスのように重ね合わせたかったからです。そして、その「私たち」の中に、登場する10人と著者の5人だけでなく、読者の皆さんにもぜひ入ってきてほしい。日常の生活の中で声を上げたいと思うときが、男性だって女性にだってノンバイナリー(Non-Binary)の人にだって必ずあるはずで、そういうときにこの本が背中を押したり、力になれるといいなと思っています。
実際に声を上げるということは、すごく大変なことです。勇気も要るし、いろいろな障壁があって、声を上げない理由は山ほどある。だけれども、この本が、勇気を出して声を上げてみようかなと思うようなヒントを提供することになればうれしいです。
それと、声は、誰も聞いてくれる人がいなかったら意味がありません。だから、声を上げるだけではなくて、声を聞く、耳と頭と心をオープンにして人の声をちゃんと受け止めて聞くこと、聞いた上で自分なりのサポートなり何なりをすることも、とても大事。そういう意味も込めて、「私たち」という代名詞を選んだのです。
最後に、ひとつ断っておきたいことがあります。私たち5人はアメリカ研究者なので、その専門を生かしてアメリカの事例にフォーカスした本をつくりましたが、「アメリカは進んでいる、それに比べて日本はダメだ」ということを言いたいのでは決してありません。本を読んでいただければ、アメリカにはジェンダー、人種、社会階層などの軸によって大きな構造的不均衡や差別があり、多くの人々がそれに苦しみ、挫折を繰り返しながら闘ってきたことがわかるはずです。
坂下 この本が「偉人伝」ではないことはとても重要な点です。私たちは「偉人」たちの成功譚ではなく、バックラッシュや挫折を経験しながらも活動を続ける人びとの姿を描くことに努めました。そうした物語を読者の皆さんにもぜひ身近に感じてほしいと思います。
私は今まで教科書や専門家向けの論文などいろいろなものを書いてきましたが、今回の『私たちが声を上げるとき』がいちばん一般の読者にリーチできるものが書けたという手応えを感じています。自分たちで書いておいて何なんですけど、この本、すごく気に入っているんです!(笑)

>>(前半記事)アメリカ現代史に刻まれる「声を上げた女性たち」 彼女たちの正義と信念から学ぶこととは
本書については、以下にも関連記事が掲載されているので、併せてご覧ください。
●『公研』2022年6月号「座談会」
● 毎日新聞 書籍紹介記事

坂下史子
立命館大学文学部教授。神戸女学院大学文学部を卒業後、同志社大学大学院アメリカ研究科で修士号、ミシガン州立大学大学院文芸研究科で博士号取得。専門はアメリカ研究、アフリカ系アメリカ人の歴史と文化。共編書に『よくわかるアメリカの歴史』、Transpacific Correspondence: Dispatches from Japan’s Black Studies、共著書に『「ヘイト」の時代のアメリカ史―人種・民族・国籍を考える』、 Gender and Lynching: Politics of Memoryなど。

吉原真里
ハワイ大学アメリカ研究学部教授。東京大学卒業後、ブラウン大学アメリカ研究学部で修士号、博士号取得。専門はアメリカ文化史、アメリカ=アジア関係史、ジェンダー研究、カルチュラル・スタディーズなど。日本語の著書に『アメリカの大学院で成功する方法』『ドット・コム・ラヴァーズ』『性愛英語の基礎知識』『ヴァン・クライバーン国際ピアノ・コンクール』『「アジア人」はいかにしてクラシック音楽家になったのか?』など、その他英語の著書多数。