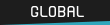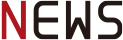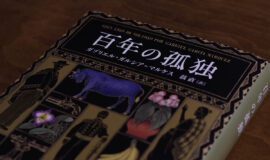かつて「大学」といえば、教育と学びの場というイメージが一般的だった。だが今、大学が果たすべき役割は大きく変わりつつある。科学技術の進化、社会課題の複雑化、そして国際的な研究競争の加速──これらに対抗し、未来社会を支える「知の拠点」として、大学は進化を求められている。
そうした中、立命館大学が国の大型研究支援事業である「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」および「宇宙戦略基金・SX研究開発拠点」に採択された。この事実は、これまでの私立大学の実績をふり返っても異例なケースだといっていい。なぜいま大学に研究力が求められているのか。そして、立命館はその競争の中で何を目指そうとしているのか──。立命館産学連携推進本部副本部長や研究部事務部長も務める野口義文副学長に聞いた。
● 教育から研究へ。大学の価値に大きな転換点が訪れている
● 日本のノーベル賞受賞は危機的状況!?
● 令和のトップ30大学。過去の勢力図に変化あり
● 宇宙研究でも存在感を高める立命館大学
● 未来に向けて社会とともに歩む「研究大学」の使命
「教育」だけでは生き残れない 大学に求められる“本当の価値”
いま、大学に課される役割は大きく変わろうとしている。求められているのは、単なる学びの場ではなく、社会を動かす“知のエンジン”としての機能だ。
「今後、大学が社会から評価されていくための軸は“研究”だと思っています。もちろん、教育は今も昔も大学の根幹ですが、それだけでは十分ではない。社会課題を見据えて、本質的な研究テーマにどれだけ挑戦できているか。そしてその成果を、社会や産業界とどう結びつけていくか。そうした研究の質と展開力こそが、これからの大学にとって決定的な価値になるのです」(野口副学長、以下同じ)
研究開発によるイノベーションは、もはや企業や国の専売特許ではない。大学もまた、社会変革のフロントラインに立つ存在になりつつある。そして、このような認識の変化を後押しするように、日本政府も動き始めている。
「いま国は“10兆円ファンド”を立ち上げて、大学の研究力強化を国家レベルの戦略に据えました。これは、単なる補助金とは違います。研究力がある大学に集中的に投資し、世界に伍する拠点を育てようという本気の仕組みです。教育だけでなく、研究の実績が“大学の生命線”になる時代が目前に来ています」
その波は私立大学にも及ぶ。従来、研究力で優位にあった国立大学に対し、私立がどう存在感を示せるか。そこには新たな戦略と覚悟が問われる。
「私学の中でも“教育に強い大学”という印象を持たれてきた立命館ですが、実は研究面でも地道に取り組んできました。ここで問われるのは、大学のあり方そのもの。これからは、社会から本当に必要とされるテーマを主体的に見極め、他大学や企業とも連携しながら、社会変革に貢献する研究をどう生み出していくかが鍵になります」
大学は、知を育む場であると同時に、社会の未来をかたちづくる場へと進化しつつある。その最前線に、いま静かに変化の兆しが生まれている。
日本の研究競争が直面する危機 10兆円ファンドと国際的な研究力の課題
今、日本の科学技術力が失速の瀬戸際にある。その象徴的な出来事として、関係者の間で語られているのがいわゆる「2030年ノーベル賞問題」だ。2000年代後半以降の研究成果に目立った国際的インパクトが見られないことから、2030年ごろには日本人の受賞が激減するのではないかと懸念されている。
「ノーベル賞は、だいたい20年から25年前の研究成果が評価される傾向にあります。つまり、2030年に受賞の対象となるのは、2005年から2010年ごろに生まれた論文や研究業績なんですね。その頃の日本の研究は、量・質ともに決して悪くはないものの、国際競争力という点ではやや厳しい状況にあったと思います。近年は、iPS細胞研究の山中先生をはじめ多くの研究者が成果を上げてきましたが、自然科学分野(物理学、化学、生理学・医学の3つの分野)の今世紀に入ってからの国別の受賞数で見ると、かつてアメリカに次いでいた日本が、今ではイギリスに並ばれています。このままでは本当に低迷期が来るかもしれない──そんな危機感を強く持っています」
研究力の低下は、基礎科学だけでなく、AIや半導体などの先端分野にも及ぶ。野口氏は、日本がいま直面している状況について、さらにこう続ける。
「つい最近発表されたAI分野の世界大学ランキングでは、トップ100に日本の大学が一校も入っていませんでした。唯一東京大学が128位にランクインしているのみで、アメリカの12大学、中国に至っては49大学がランクインしている。この差は決定的です。これからの社会では、生成AIや人工知能がさまざまな産業や社会システムの中核になっていく。そこにおいて日本の大学がこれだけ出遅れているという事実は、非常に深刻だと感じています」
特に衝撃的だったのは、中国・浙江大学発の生成AI「DeepSeek」が世界の注目を集めたことだという。
「OpenAIがトップを走っているのはご存じの通りですが、その次に浙江大学の研究者たちが開発したAIが続いている。しかも、NVIDIAも驚くほどの完成度です。もう“新興国の追い上げ”なんて生やさしい話ではない。すでに日本は、多くの分野で追い越され始めているのです」
こうした現実を受け止めたうえで、大学が果たすべき役割とは何か。その答えを探るために、日本各地の大学が動き出している。

“令和のトップ30”に名を連ねた意味 立命館が掴んだ歴史的転機
このような状況の中、2024年、立命館大学は日本の大学政策において歴史的な転機とも言える、文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」に採択された。これは、政府が10兆円ファンドによって研究力強化を国家戦略とするなかで、重点的に支援するJ-PEAKSも含めた30の大学群、いわば“令和のトップ30”を形成しようとする試みだ。
「2002年に始まった21世紀COEプログラム、そして後継のグローバルCOEプログラムなどを経て、ようやく“研究大学群”としての再構築が本格的に始まりました。J-PEAKSの採択は、その中でもとりわけ重要なポジションを示しています。10兆円ファンドの中でも国際卓越研究大学が数校、J-PEAKSとして25大学が選ばれ、あわせて30大学。私はこれを“令和のトップ30”だと考えています」
J-PEAKSで配分されるのは、研究費ではなくマネジメント経費──つまり、研究の基盤や組織体制を整えるための資金である。その金額は55億円。設備や人材、国際連携の強化など、大学としての“経営力”を問われる事業でもある。
「55億円という規模は、私の30年以上のキャリアの中でも前例がない水準です。しかもこの経費は、先端設備・機器だけではなく、人件費やガバナンス強化にも使える。大学が自らの研究戦略を描き、それを実行できる体制があるかが問われた。その意味で、この採択は立命館にとって大きな“信頼の証”でもあります」
注目すべきは、私立大学からの採択が25校中4校と非常に限られていた点だ。その中に立命館が選ばれたことは、国からの評価のあり方が変わり始めていることを示している。
「私立大学としてJ-PEAKSに採択されたのは、慶應義塾大学、沖縄科学技術大学院大学、藤田医科大学、そして立命館大学の4校だけです。これは本当に大きなことです。国の側からも“立命館がこれからの研究大学を担える存在である”と認識された。産学連携、国際展開、地域貢献、組織マネジメントなど、これまで地道に積み重ねてきた取り組みが評価されたのだと受け止めています」
これまで「教育の立命館」と語られることが多かったこの大学が、今や“日本の研究大学群”の一角に本格的に食い込もうとしている。J-PEAKSの採択は、単なる大型予算の獲得ではなく、大学の在り方そのものを進化させる、大きな一歩となった。

SX研究開発拠点に見る立命館の飛躍 宇宙研究で示した可能性
2024年、立命館大学はもう一つの重要な採択を受けた。宇宙戦略基金による「SX研究開発拠点」の選定である。宇宙関連研究の中でも特に競争率が高く、国内有数の研究機関がひしめく中での採択は、学内外に大きな驚きをもって受け止められた。
「もともと立命館は長年宇宙を専門的にやってきた大学ではありません。2023年に宇宙地球探査研究センター(ESEC)を立ち上げたばかりで、そこから2年も経たない中での採択だったわけです。にもかかわらず、旧帝大や国立天文台など、日本の宇宙研究を牽引してきた強豪の中に割って入ったというのは、まさに“宇宙業界に激震が走った”と思います」
同じくSX研究開発拠点に採択されたのは、東京大学(2件)、名古屋大学、国立天文台、そして立命館大学──わずか5件。つまり、国内の宇宙研究において「選ばれた存在」としての地位を得たと言える。
「我々の提案が評価されたポイントは、“これまで”ではなく“これから”だったと思います。つまり、立命館の宇宙地球探査研究が今後どこまで伸びていくか、そのポテンシャルに対する期待です。加えて、もうひとつ大きかったのは、宇宙分野の専門企業だけでなく、いわゆる“非宇宙企業”と連携していたこと。例えば、京都の島津製作所さんや、関西に基盤を置く素材や加工メーカーさんなど、多様な企業と組んで“これからの宇宙”を考える枠組みが作れたことが、非常に高く評価されたのだと認識しています」
実際、SX研究開発拠点は、宇宙戦略基金の中でも最も提案側の設計自由度が高い反面、審査の厳しい分野だ。56件の応募があり、最終的に5件が採択された。競争率は11倍を超える。
「短期間で環境を整備し、研究チームを結成し、トップのリーダーシップのもとで申請を行った。そして何より、“宇宙は一部の専門家だけのものではない”というメッセージを込めた提案を形にできた。これこそが、教職協働やオープンイノベーションを標榜する立命館らしいアプローチだったと感じています」
宇宙という国家戦略の最前線で、立命館大学の名前が並ぶ時代が来た。その現実は、大学という存在のあり方をも大きく変えようとしている。
研究が社会を変える 次世代を担う人材と大学の新たな価値へ
立命館大学では現在、「次世代研究大学構想」に基づき、新たな研究組織「次世代研究機構」の立ち上げを進めている。その一つの参考モデルとなっているのが、英国・オックスフォード大学のマーティン・スクールだ。
「マーティン・スクールは、社会課題を解決するための研究ユニットをいくつも持ち、企業や行政とも連携しながら、知を社会に還元しています。立命館でもまず3つ程度の社会課題を柱に、そこに人・モノ・資金を集中投下して“知のサプライチェーン”を作ることを検討しており、それがこの構想の中核となります。数年後には、研究成果をもとに社会や政策に提言できるような枠組みを整えていきたいと考えています」
加えて、もう一つの大きな柱が「博士人材のキャリアパス支援」だ。立命館大学では現在、約800人の博士後期課程の学生が在籍し、その7割強が人文社会科学系だという。
「博士の育成には高度な研究力が必要です。つまり、博士の数が多いということは、大学としての研究の“土台”がしっかりしているということ。今後はその人材をアカデミアにとどめるのではなく、企業にも送り出していきたい。特に人文社会科学系の博士人材は、社会課題の解決において今後ますます重要な役割を果たすはずです。研究力と学際性・社会実装力・社会包摂性を兼ね備えた人材を世に送り出すのが、研究大学としての使命だと思っています」
こうした多面的な取り組みの背景には、「大学の在り方を変えていく」という強い意志がある。
「これまで“研究大学”といえば、旧七帝大や東京科学大学、筑波大学、早慶といった、例えば一部の大学に限られて語られることが多かったと思います。しかし本来、研究の価値はもっと多様で開かれたものであるべきです。立命館は、研究を軸に社会とつながり、多様なステークホルダーと共創・共鳴する大学を目指していきます。“意志あるところに道は拓ける”。私たちはこの信念を胸に、新たな大学像を描いていく覚悟です」
今、大学は“進学のための場所”から、“社会の未来を共に創るプラットフォーム”へと変わりつつある。就職や資格の取得だけではなく、未来を支える知を育み、その知を社会へと還元していく役割が、大学には求められている。そしてその動きは、決して限られた大学だけのものではない。立命館大学のように、地域に根ざしながらも世界とつながる研究拠点が生まれつつあるいま、大学の勢力図は、着実に書き換わり始めている。

野口義文
学校法人立命館理事、立命館大学副学長(研究担当)。2011年国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)イノベーションコーディネータ賞を受賞、2024年独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)功労者感謝状を受理。学外委員として文部科学省大学研究力強化委員、理化学研究所事務アドバイザリー・カウンシル委員、茨木市産業振興アクションプラン推進委員会委員長等を務める。現在立命館大学研究部門の責任者として、研究高度化を牽引。