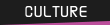前回の記事では、飲食プロデューサーの稲田俊輔氏と立命館大学文学部の加藤政洋教授が、京都食堂の魅力について深く語りあった。出汁のおいしさのエピソードや、上おき(具)の構成を紐解きながら、「京都食堂が提供するメニューは、本質的には京料理と変わらない」という結論にいたる対談は、非常に興味深いものだ。
一方で、そんな京都食堂も大きな課題を抱えている。高品質な料理を提供し続ける一方で、その存続には多くの困難をともなうのだ。対談の後編では、京都食堂のクオリティを保ちながら、どのようにしてその伝統を継承していくことができるのか、京都食堂の未来の可能性を探っていく。
>> 前編「飲食プロデューサー稲田俊輔対談① いま「京都食堂」がおもしろい」を読む
● 京都食堂のクオリティは京料理と同レベル
● 新店やクラスチェンジもある東京の蕎麦屋との違い
● 上流と下流が重なっているのが京都の食文化
● 地元の人が自覚していない“すごさ”を表現すること
京都食堂は安すぎる! クオリティが高すぎるからこそ心配なこと
現在、いわゆる個人経営の“食堂”や飲食店の比率は急激に減り続け、代わりに数々のチェーン店が外食産業を担っている。時代の趨勢といえばそれまでだが、京都食堂もまた、そのような状況の中で数を減らしている。
加藤「この先、これまでのようなスタイルの京都食堂が新しく誕生することはまずないと思います。幸いにして、若い世代に事業承継できているケースもありますが、基本は店主の高齢化の波もあり、いつまで続けられるかという状況です。事業承継といっても、おそらくわれわれより年長の方が多いくらいですから…。この先どこまで“持ちこたえられるか”は、やはり心配ですね」

稲田「私も飲食店をさまざま手がけてきましたが、外から見ていて率直に思うのは、やっぱり『安すぎる!』ということなんです。世間がこれだけ値上げの流れになっている昨今でさえ、なかなか値上げしませんからね。
この対談前に、実は一軒食べてきたんですが、『もうこれは完全に京料理じゃん』というクオリティなわけですよ。素材の使い方から出汁の引き方、すべてが。そしてお代は、これでも多少値上げしているかもしれないけれど、850円なんですね。それはおかしいだろうと(笑)。
でも一方で、地元の方たちにとっては『その金額感が当たり前』という捉え方は当然あるだろうと思います。日常的なランチに『1,000円超えるなんて』という感覚も理解はできる。ただ、京料理のお店で2万円取るようなコースの『台のもの』として出てきても全然おかしくないようなクオリティの料理が、あの値段で、しかもお腹いっぱい食べられるというのは、今後の存続を考えても心配な部分です」
京都食堂はこれ以上「本格的に」できない!? 東京の蕎麦屋との構造的な違い
稲田「たとえば東京を見ると、京都食堂にあたるのは、いわゆる蕎麦屋さんになるでしょう。東京でも、確かに昔ながらの街の蕎麦屋は減りつつありますが、その一方で新しい店がオープンすることも珍しくない。蕎麦屋に関しては、昔ながらの出前中心でやっていた店を、2代目3代目の後継者が『もうちょっと本格的な方に方向転換する』みたいなことが盛んに起こっています。
なぜそのような転換が可能かといえば、簡単にいえば『お金が取れる』からなんですね。東京の蕎麦屋では、いわゆる『そば前』のような形で、お酒とおつまみを楽しむような使い方が定着しています。今の蕎麦屋さんって、伝統的なそば前だけじゃなくて、例えば『いぶりがっこクリームチーズ』のような居酒屋的なものを取り入れたり、全国の地酒に力入れている店もあります。確かにそばの単価だけで見ると京都食堂と変わらないけれど、お酒飲んでつまんで…ってなると、あっという間に4,000円5,000円の世界になってくるわけです。
京都食堂の場合は単品が安いのに加えて、『サブメニューも加えて単価を積み上げよう』みたいな色気が全くありません。ものすごいサービス精神ですし、伝統としての良さなのですが、その前提が変わらない限り、新しい形態で京都食堂を持続させていこうという人は出て来づらいと思うんです」

加藤「今の稲田さんのお話は、本当によくわかります。『ベクトルの違い』なんですよね。たしかに蕎麦屋だと十割とか手打ちにこだわって、ダウンライト照明のジャズ系音楽が流れるお店というイメージもすぐにわきますし、その方向で伸ばせる可能性ってすごくありますよね。さきほど『本格的な方向に』とおっしゃいましたが、京都食堂でそれをやろうとすると、『メニューを絞って、余計なオムライスを排除…』みたいにシンプルにして、バラエティの豊富さというアイデンティティを損ねる方向になってしまう」
稲田「少し乱暴な言い方かもしれませんが、日本の食文化には上流下流のようなものがあります。上流の食文化って、京都で生まれて関西で育ったいわゆる懐石料理的なものといえるでしょう。対して下流にあたるのは、大衆食堂などの庶民的な味の世界です。日本全国どこにでも、縦割り的なローカル食文化が根付いています。つまり、上流は全国共通だけど下流はローカルみたいな構造になっている。
ただし、京都は違うんです。下流にあたる京都食堂が、上流の懐石料理のエッセンスを持ってしまっているわけですから」
加藤「そうなんですよ。だから京都食堂がアッパーになったとしても、何も変わりようがない。おはぎも出しますし、お寿司も出しますし」
自覚されていない「素晴らしい食文化」を持続させていくために
稲田「僕が京都で学生だった時には、もちろん京料理なんか食べにいくことはありませんでした。でも、京都食堂のおかげで京料理の本質的な部分は掴めていたと思うんですよね。後に、いわゆる“ちゃんとした”京料理を食べた時に、『結局、あの時食べてたうどんとか定食とかと一緒じゃん』って感覚を持ったくらいです。確かに松茸が入ったり、器が豪華だったりするかもしれないけど、出汁の味は一緒なんだなぁみたいな。
京都で過ごす日常の中で、本当にいいものを食べていたんだなと、あらためて思います」
加藤「文化としての食を研究していると、料理というのは長い時間の中で伝播していって、知らず知らずのうちにさまざまな地域に根付くということを繰り返してきたことがわかります。同じルーツを持っていても、それぞれの地域の食文化と融合するなかで変化もする。料理を“旅する文化”と捉えると、食文化って地域だけの閉鎖的なものではないという思いを強くします。
京都にいると、京都食堂はあまりにも当たり前で、お店をやっている人たち自身がそのすごさに気づかない部分もあるでしょう。ローカルなお店をやっている当の方たちがそのすごさに無自覚であることは、外から見るとたくさんありますよね」

稲田「本当にそうなんです。昔から長野県の名物である『おやき』の大ファンなんですが、来年100周年を迎えるおやき店に関わらせていただいて長野に行くと、長野の方はおやきのことを全然すごいと思ってないんですよね。それどころか、むしろ『他所様に見せるのは恥ずかしい』くらいの感じだったりする。
長野でいうと、『醤油豆』というローカルフードもそうです。僕の中では、最低でもいぶりがっこレベルで大ブレイクするポテンシャルを持っていると思ってるんですけど、地元の人は『あんなの貧乏臭くて恥ずかしい食べ物』と思っているらしいんです。
長野に限らず、そういう食文化は全国にまだまだたくさんありますよね」
加藤「文化としての食は地域に根ざしたものですから、たしかに『他所様』の視線を気にすることなどなかったでしょうし、あまりにも当たり前にすぎる存在なんですよね。でも、食堂のかつ丼ひとつとってみても他地域にはみられない特色がありますし、中華そばの上おきにしたってナルトばかりではありませんよね。ピンクに着色された蒲鉾だってある。
さきほど『伝播』という言葉を使いましたが、もう少し丁寧にいうと、かつ丼であれ中華そばであれ、それらには起源(roots)があって、移動の経路(routes)があって、そしてある地域で時間をかけて根付いてきたわけです(rootedness)。一杯の丼のなかに、文化の移動と地域の歴史を織りなす物語が、人知れず隠れていると想像するだけでも愉しいですよね。
ぜひ身近な食堂に足を運んで、丼のなかの物語を垣間見てほしいな、と思っています」

稲田俊輔
料理人・文筆家。南インド料理専門店エリックサウスでは総料理長を務める他、様々なジャンルの飲食店をプロデュース。レシピ本を始め、エッセイ、小説など食にまつわる著作も多数。近著は『料理人という仕事』(筑摩書房)、『現代調理道具論』(講談社)。

加藤政洋
1972年長野県生まれ。専門は文化・歴史・社会地理学。著書に『おいしい京都学 料理屋文化の歴史地理』(河角直美と共著、ミネルヴァ書房)、『酒場の京都学』(ミネルヴァ書房)、『大阪 都市の記憶を掘り起こす』(ちくま新書)などがある。現在、『京都食堂探究』の続二編を準備中。近年は友人や学生たちとともに、沖縄の都市誌も探究しています。旅するがちまやー(沖縄の言葉で「食いしん坊」を意味します)。