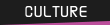2022年の第167回芥川賞は、高瀬隼子さんの『おいしいごはんが食べられますように』(講談社)に与えられた。今回は、高瀬さんの母校でもある立命館大学の文学部校友会で明かされた、学生時代から続く創作活動や、ストーリーを立ちあげていく視点、さらにその背景にある哲学的思考にも触れながら、新たな才能に迫っていく。
● 『おいしいごはんが食べられますように』はこうして生まれた
● 登場人物たちが“動き出す”まで
● ごはんは“おいしくて、温かいもの”でなくてもいい
● 「むかつき」の観察と哲学専攻の視点
● 働きながらも書き続ける、創作の原動力
同じ職場の男1人と女2人。「ごはんの話」を書くつもりはなかった!?
『おいしいごはんが食べられますように』の物語は、同じ職場で働く3人の登場人物を中心に回っていく。職場でも要領が良く、飄々と世を渡っていくような男性「二谷」。体が弱く、皆が守ってあげたくなる雰囲気をまとう、二谷の恋人「芦川さん」。そして、そんな芦川さんが苦手で、辛いことも自分の力で乗り越える強さを持つ女性「押尾」。三角関係でもなく、愛憎劇でもない。過ぎていく淡々とした日常に、徐々に不穏な影を落としていく“いじわる”とは?
その真相は、実際に本を手に取っていただくとして…。
タイトルに「おいしいごはん」というキーワードが盛り込まれた物語が「ごはんの話を書くつもりがなかった」ところから生まれたとしたら、みなさんはどう感じるだろうか?
さっそく、高瀬さんに聞いていこう。
背景にあった膨大な文章やメモ 「登場人物が動き出す」とは、どういうことか
「物語の着想はいつも“ない”んです(笑)。今回は『ごはん』の話ですが、ごはんの話を書くつもりはありませんでした。最初に『二谷』という男性の登場人物が生まれ、彼を主人公に書いてみたくなった、というのが原点です」(高瀬隼子さん、以下同じ)
実は高瀬さんの創作の初期は、必ずしも物語の形にはなっていない「さまざまな文章やメモ」なのだという。

「二谷も仮名の『Aさん』くらいから始まりました。年齢も最初は決まってなくて、どうやら20代後半くらいかな、と少しずつ頭に描き、文字にしていきます。会社員で、埼玉の会社で、この人はあんまりご飯が好きじゃないな。本当は文学部に行きたかったけど、経済学部に行ってしまった人で。……ということは家には単行本ではなくて文庫本がいっぱいありそうだな、といった感じです。
家の様子も箇条書きで、間取りなんかもメモしますね。私は絵が描けないので、文章で『ベッドは狭い』とか。
そういうことを200枚〜300枚くらい書いていると、文章を通じて3〜4カ月のあいだ毎日、二谷さんと付き合っている感じになります。二谷さんという存在が『実在する知り合い』のようになってくる。そうなると、あるシーンのことを考えた時に、私の思考のフィルターを通さずに二谷が動いてくれるようになります。
冒頭で3人の上司である男性が、芦川さんのペットボトルに口を付けるという気持ち悪いシーンがあるのですが、私が『二谷はどうするだろう』と思うより先に、彼は『ゆるゆると頷』いていました」
作家が言う「キャラクターが動き出す」というのは、このような瞬間を言うのだろう。徹底的に登場人物のディテールを書きとめ、自分の間近に実在するかのような存在感を作り上げる過程で、“着想のない物語”が育っていった。
ごはんは“おいしく、温かいもの”でなくてはいけないのか?
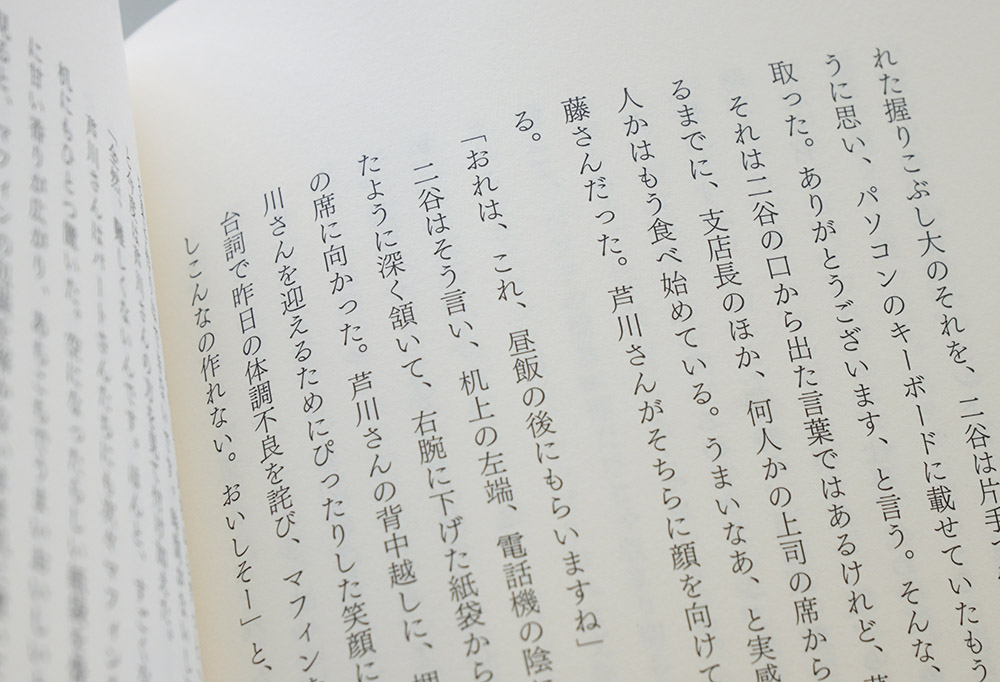
「ごはん」をテーマにした創作は多岐にわたるが、その多くは食事という行為を通じて、人の心の温かさや、感情の高まりなどを表現しているといっていい。一方で、『おいしいごはんが食べられますように』では、「ごはん」はむしろ“不穏さ”を生む装置であり、二谷に至っては食について1ミリも興味がないどころか、憎しみさえ抱いているかに見える。
「『ごはん』というキーワードを温かいものとして書いている作品が多いと思うのですが、私にはずっと何でだろうという気持ちがありました。例えば漫画だと、緊迫した場面でおなかがグーっと鳴ったら『あはは』と笑うのがお約束だし、食いしん坊キャラはいい人じゃないですか。ルフィも漫画肉を持っているし。
私はずっとそれに違和感がありました。別に小食なヒーローがいてもいいし、ご飯はまずくて嫌いというヒロインがいてもいい。食欲と人格は絶対に別物なのに、イコールで結び付けられているのが不思議で。今回のタイトルも、『おいしいごはんが食べられますように』と書いているだけなのに、これだけを読むとほっこりした話のような感じがする。すでに自分の中にフィルターがある感じがして、そこへの反感があります」
哲学を専攻した学生時代 「むかつき」のメモから生まれるリアル
世の中にある多くのステレオタイプ、紐づけられた先入観。そんな「当たり前」への根源的な疑問は、どこから出てくるのか。その原点は、立命館大学で専攻した、哲学の世界に見ることができる。
高瀬さんは卒論でライプニッツをテーマにし、世界に存在する「悪なるもの」にどう向き合っていくべきかを論じた。「むかつくことだらけの世界」を敏感に察知し、先入観から自由な視点でシーンを切り取るセンスは、学生時代の学びや経験が培ってきたものでもあるのだろう。
「今回、立命館大学文学部の同窓会で、当時の指導教員でもあった谷徹名誉教授が、私の作品をテーマに講演してくださいました。私は当時の卒論の内容をすっかり忘れてしまっていたのですが、『おいしいごはんが食べられますように』につながるような言及があったことをライプニッツのモナド論を引き合いに出して指摘いただき、無意識を覗かれるような感覚に、変な汗をかいてしまいました。
日常的に感じる『むかつき』は、よくメモしているんですよ。私は本当に物事をすぐに忘れてしまうので、メモしておかないと『むかついたこと自体』を忘れてしまうんです。嫌なこともすぐに忘れてしまうので、後になって『あんな嫌なことがあったのに忘れてしまった自分』にまたむかついたり(笑)」
世間に溢れる不条理や悪は、「むかつき」という形で人の心を動かしている。自分自身はもちろん、友人や同僚の「むかつき」に目を向ける習慣は、高瀬作品の登場人物が持つリアルさと無関係ではないだろう。
「書いていないと体調が悪くなる」 高瀬隼子さんを作家たらしめた熱量
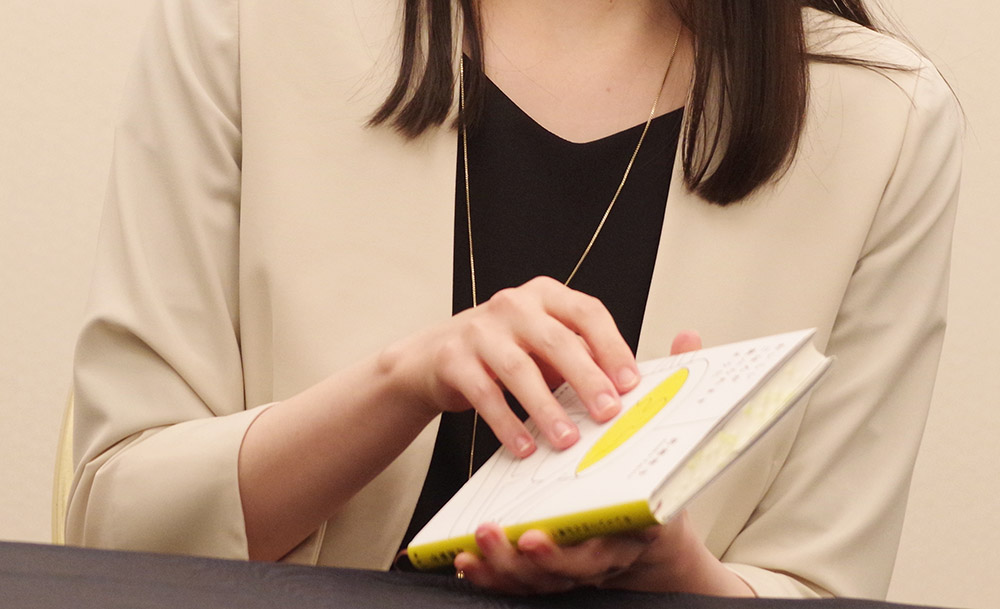
「小学校の低学年からずっと物語を書く人になりたかった」という高瀬さん。立命館大学では文芸創作同好会に所属し、大学2回生からは、各種「新人賞」に投稿を繰り返し、作家としてのデビューを目指してきた。
『おいしいごはんが食べられますように』は3冊目の単行本となるが、現在もなお、普段は企業で働きながら、毎日の執筆を日課にしているという。大学時代から社会人として勤める現在に至るまで、毎日書き続け、創作し続けること。それは並大抵のことではない。
「よく、働きながら書き続ける原動力を聞かれます。でも、みなさんも夜は、テレビや映画を見たり、本を読んだりしていますよね。私にとっては、書いたほうが“落ち着く感じ”はあって、例えば3日間小説を書かない日が続くと、体調が悪くなってきます。気持ち悪いなと思ってしまう。
もしかするとそれは、焦りから来ているかもしれないのですが、その感覚はデビュー前からありました。書くと落ち着くので、たぶん好きで書いているのだと思います。
サークル活動で立命時代から今もずっと一緒に創作をしている人たちも、みんな勝手に書いちゃってるんですよね。デビューしている・していないは関係なく、書きたい衝動があるのだと思います」
文芸創作同好会での活動では、仲間の作品の感想を披露しあう合評会があったという。合評会のルールは「書いてきた本人はひと言もしゃべってはいけない」こと。
「終わったらしゃべっていいけど、『あなたが何を言おうと作品から読み取れなかったら、それは“ないこと”だから』という考え方を、サークル活動を通じて学びました。本当にそのとおりだなと思います。今も社会人サークルとして、同じメンバーで合評を続けています。みんな社会人で住まいもばらばらなので、SkypeやZoomでやるのですが、作者はミュートにしないといけません。『作品は手を離れたら読者のもの』という考え方は、文芸創作同好会で教えてもらったと思います」

芥川賞の受賞を「これから頑張れ」というメッセージだと受け取っている、と語る高瀬隼子さん。休むことのない創作習慣と、社会にあふれる「むかつき」に向ける眼差しは、次にどんな物語をみせてくれるだろうか。次回作を楽しみに待ちたい。

高瀬隼子
2011年に立命館大学文学部哲学専攻を卒業後、企業で勤務しながら執筆した小説『犬のかたちをしているもの』で「第43回すばる文学賞」を受賞、文芸誌『すばる』に掲載されデビュー(単行本は集英社、2020年2月刊)。『水たまりで息をする』(集英社、2021年7月刊)が「第165回芥川龍之介賞候補作」に選出された。近著である『おいしいごはんが食べられますように』(講談社、2022年3月刊)は、「第167回芥川賞候補作」に2年連続でのノミネート。同書は第167回芥川賞を受賞し、栄えある芥川賞作家となった。