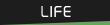今年(2019年)10月から幼児教育・保育の無償化が実施される。幼稚園や保育所などを利用するすべての3〜5歳児で利用料が無償になるため、小さな子どものいる家庭の多くでは家計が助けられることは間違いない。
しかし一方、「保育士の待遇を改善して人材の確保から着手すべき」「無償化が保育需要を掘り起こすため、待機児童問題が悪化する」という反対意見も根強く、子育て世帯の働きやすさにどれほど結びつくかは疑問も残る。
また、人口が1億超にもかかわらず高齢化率が世界ワーストの日本では、年金や医療費など社会保障支出が増え続けることは必然。教育や家庭のための公的支出が将来大きく拡大する可能性も、残念ながら小さい。
家庭をめぐるシビアな状況の中、共働きの2人がワークライフバランスを実現するには、どんなポイントに気をつけるべきだろうか? 『結婚と家族のこれから 共働き社会の限界』(光文社新書)、『仕事と家族 日本はなぜ働きづらく、産みにくいのか』(中公新書)などで家族や労働について論じている筒井淳也教授(立命館大学 産業社会学部)に話をうかがった。
家事分担で気をつけるべきポイントは?

労働には、対価としてお金が支払われる「有償労働(paid work)」と、家事・育児などの「無償労働(unpaid work)」がある。男女の性別分業がもっとも広まっていた70〜80年代には、男性が有償労働で家計を支え、女性が無償労働を行って家庭を運営するのが、よく見受けられる家庭の姿だった。
しかし現代ではフルタイムで働く女性が増え、女性の有償労働時間は著しく増えた。男性の有償労働時間はやや減少しているという。では無償労働の時間はどう変化したのだろうか?
家庭の外で働くようになった女性では減り、それを補うべく男性で増えたと考えるのも自然だが、現実はそうではなかった。
「女性の無償労働時間は、70〜80年代と比べてたしかにかなり短くなりましたが、不思議なことに男性の無償労働時間はほとんど変わりませんでした。つまり、家庭全体における無償労働時間は大きく減りましたが、それは主に家事の自動化や外食・中食の普及などに起因し、男性による貢献はほとんど無かったのです。
最近の男性は家事・育児に協力的なイメージもありますが、以前に統計データを取ったところ、男性の家事時間は十年間で一日10分弱しか増えていないという結果が出ました」
(筒井教授、以下同じ)
男性は有償労働が減ったため家事や育児に参加する余地も増えたはずだが、そうはならなかったというのが実情ということだ。
「男女の無償労働をもっと均等にすることが、余裕を持って家庭生活を運営するための第一歩といえます」

しかし、家事・育児分担にはトラブルの種が多い。その一つが要求水準の不一致だ。料理や掃除などの家事に対して、一般に女性のほうが高いクオリティを求めるケースが多い。特に、専業主婦として家事をこなす母親を見て育った女性の中には、たとえフルタイムで働いていても母親と同水準の家事をこなそうとする人もいる。必然的に男性に対する要求も高くなってしまい、家事に不慣れだったり、そもそも要求水準が高くない相手との対立につながるケースもある。
「会社の仕事とは違って、家庭の仕事の水準は夫婦・カップルの2人で決めざるを得ず、決着が付きづらい。お互いに『自分の方が正しい』と思いがちです」
日本の家事水準は海外に比べて高く、いわば「手を抜く」余地は大きいという。そもそも、フルタイム共働きの2人が、性別分業型の家庭と同じ家事クオリティを保つのは不可能だ。
「ただし会社の仕事と同じで、不慣れな人が初めて家事・育児に参加するときは教育などの『初期投資』は必須です。見守る側も最初は寛容な気持ちで協力するほうがいいでしょう」
ワークライフバランスの「ライフ」とは? 家の仕事もしない自由な時間を確保すべし
フルタイムで働きながら子どもを育てる夫婦・カップルにとって、仕事と家庭の両立は最重要課題だろう。しかし筒井教授は、「仕事と家庭の両立を『ワークライフバランス』と呼び、最終目標にするのは危うい」と話す。
「ワークライフバランスという言葉ではたいてい、『ワーク=有償労働』『ライフ=家事・育児を含む家庭生活』とイメージされがちです。しかしこの考え方では、生活のほとんどが有償または無償の労働に占められ、心くつろぐ時間がなくなってしまいかねません。大切なのは、仕事も家事・育児も行わない自由な時間を確保すること。この時間こそワークライフバランスの『ライフ』と呼ぶべきです。
家族といるとくつろげない人もいるはずで、“家庭の時間=ライフ”と機械的に考えると、『家での時間も多いのになぜか気が休まらない』と知らずしらず気持ちの余裕をなくしてしまう危うさがあります」
仕事や家事・育児をすべてこなすのは神経を使う難題だが、それが達成されればすなわち素晴らしい生活といえるわけではない。過ごし方を自分だけで決められる自由な時間、すなわち本当の「ライフ」は男性にも女性にも等しく必要だ。
「家庭」の存在を前提にしていいのか
ここまでは家庭の存在を前提にした議論だったが、最後に筒井教授は「ともに住む家族のいない人がいることも忘れるべきではない」と注意を促す。特に東日本大震災以降、家族の絆や家庭の良さがことさらに強調されるようになった。企業の広告でも、家族がいることによる料金メリットなどを謳うものが多い。
「しかし、世の中のすべての人が一緒に住む家族を持っているわけではありません。現代日本は、男性の4人に1人、女性の7人に1人が生涯未婚という時代。大半は結婚『したくない』というよりも『したいけれどできない』という人です。それにもかかわらず一緒に住む家族のある人だけを制度的に優遇しては不公平感が募ります。同居家族のいない人を制度的にサポートする視点も意識するべきです」
自分とは異なる立場や環境に置かれている他者を想像することが、社会で強く求められていると筒井教授は語る。そしてこの視点は、家族やパートナーを気づかうためにも欠かせないはずだ。真のワークライフバランスを実現するために必要な眼差しは、社会制度と家庭運営のどちらを考えるうえでも、同じものかもしれない。

筒井淳也
立命館大学産業社会学部教授。専門は家族社会学、計量社会学、女性労働研究、ワーク・ライフ・バランス研究。1970年福岡県生まれ。一橋大学社会学部、同大学院社会学研究科、博士(社会学)。著書に『仕事と家族』(中公新書、2015年)、『社会を知るためには』(ちくまプリマー新書、2020年)、『社会学入門』(共著、有斐閣、2017年)など。内閣府第四次少子化社会対策大綱検討委員会・委員など。