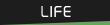立命館大学産業社会学部の丹波史紀教授は、福島県双葉郡8町村の全住民を対象にした大規模実態調査を2011年、2017年、2021年の計3回、実施してきた。継続的な調査・研究を踏まえ、丹波教授は「尊厳ある暮らしの再建こそ優先されるべき」と訴えている。「なぜ復興が進まないのか」という視点ではなく、「被災者一人ひとりに合った生活再建を進めるために」という視点で東日本大震災からの復興の過程を検証しつつ、地域社会のレジリエンスについて考察していく。
● 「レジリエンス」とは、危機的状況をはね返し、活力を回復する力
● 被災からの回復過程について、経験も知見も不足していた
● 被災から「回復」するとは、どういうことなのか?
● 多様な回復の道筋を認める「複線型復興」という考え方が重要
● 地域のレジリエンスを高める「当事者性・受援力」とは何か?
「レジリエンス」とは、危機的状況からの回復力
「レジリエンス(resilience)」という言葉をご存知だろうか?
直訳すると「はね返り、弾力、回復力」といった意味を持つ英語だが、最近は「困難や危機的状況に直面したとき、それをはね返し、活力を回復する力」を表す用語として幅広く使われるようになっている。
例えばビジネスの領域では、組織としての危機対応力や回復力の重要性に着目して、「レジリエンスの高い組織」や「レジリエンス経営」などの言い方をよく使う。また、心理学の分野では、個人の「強いストレスに直面しても、それに適応し、はね返していく力」という意味でも使われる。
今回は、この「レジリエンス」を、地域社会・コミュニティーでの実際の取り組みから具体的なイメージとして捉え直していく。“コロナ後”に向けた回復・再生を模索する動きがさまざまなレベル、さまざまな領域で取り組まれている今、地域におけるレジリエンス(回復力)はどのような現状にあるのだろうか。
はじめに、地域のレジリエンスを高めるという視点で、東日本大震災の復興から何を学び取らなければならないのかを見ていこう。
回復の長期化と知見の不足がレジリエンスを低下させる
丹波教授は「従来の災害研究では足りなかった部分があった」と、次のように語る。
「災害研究はこれまで、例えば地震や津波などの予知や防災など、なるべく被害に遭わないようすることを前提にした枠組みで行われてきました。
その成果もあり、災害発生前の事前の備えをどれだけ強靭なものにしていくかや、災害発生直後の避難や緊急対応については知見・ノウハウの蓄積がありました。しかし、被災後の回復にどういう力を注いでいくべきかについては、意外に経験が乏しいというのが実態です」(丹波教授、以下同じ)
被災後の回復については行政の仕組みも対応できていなかった。その典型的な事例の一つが、仮設住宅だ。

「被災者に対する仮設住宅の貸与期間は、原則、2年間となっています。つまり、『2年間の間に住まいを再建するなり借りるなどして地域での暮らしを取り戻しましょう』という考え方に立って、法律がつくられているのです。しかし、2年を超えても仮設住宅等から退去できず生活再建がままならない人が一定数いることは、2004年10月の新潟中越地震の後の復興過程でも指摘されていたことでした」 (丹波史紀教授、以下同じ)
この仮設住宅の問題は、法制面の不備という側面もあるが、一方で生活の再建により長い時間を要するようになっているという現実も浮き彫りにしている。被災後の回復に関する知見の不足も、生活再建に要する時間の長期化も、被災地・被災者のレジリエンス(回復力)を低下させる要因だ。
こうした東日本大震災の復興の現実の中で、丹波教授は強い課題意識を持っていた。
「東日本大震災の場合、原子力災害という特別な事情があって、回復に長期の時間が必要になっているという面はあります。しかし、岩手・宮城でも仮設住宅の撤去がなかなかできなかったことを考えると、背景に人口の減少や高齢化といった今の日本が抱える構造的な問題があって、回復に時間がかかるようになっていると言えます。
これからの災害研究は、そうした社会構造の大きな変化も踏まえ、なおかつ、長期の時間軸の中で、被災からの回復がどういう道筋をたどっていくのかを考えていかなければなりません。
さらに、長期にわたって地域社会を重大なリスクにさらすという意味では、自然災害だけでなく、感染症もあれば、気候変動もあれば、紛争だってあるかもしれません。しかし、私たちはそうしたリスクに対処する十分な経験を持っておらず、次のリスクにどう備えて、どう対応していくのかという点も含めて、回復過程の研究を進めていく必要があると思っています」
生活再建、地域復興の道筋はひとつではない

丹波教授の最新の調査(2023年)によると、働き盛りの20代から50代の層であっても3割近い人が無職の状態にあり、「長期にわたって避難生活というリスクにさらされてきたことで、人々の暮らし、仕事、健康などが蝕まれている」(丹波教授)実態が浮き彫りになった。
継続的に調査・研究に取り組む一方、丹波教授は、生活再建・地域復興に関する政策提言も行ってきた。その中で強く訴えたのは、「課題解決の道筋は単一の方向ではない」という点だ。
「被災からの回復とは、元に戻す、あるいは故郷に戻ることなのでしょうか? 一番大事なことは、人々の生活を再建し、尊厳ある暮らしを取り戻すことではないでしょうか。
故郷に戻ったから幸せだとも言い切れませんし、避難先に長くいるから不幸というわけでもないと思います。例えば、避難先で新たな仕事を見つけ、自立的な生活を送ることを目指すという選択があってもいい。いろいろな回復の道筋があって、その人その人の実状に応じた再建、回復、復興があるわけで、それらの道筋がきちんと保証されることが大切です。
2015年3月に仙台開かれた第3回国連防災世界会議でも言われていたことですが、『より良い復興とは被災前よりも良くなる』ということなんです。被災前よりも良くするために、さまざまな課題解決・改善の方法があり得るはずで、決して一律・単一な方法でやってはいけない。こうした考え方を『複線型復興』と呼んでいます。
複線型復興は、住宅の再建に関して阪神・淡路大震災のときからずっと言われてきたことで、レジリエンスを考える上でとても重要な考え方だと思います」
地域のレジリエンスを高める「多様性・当事者性・受援力」
「複線型復興」とは、多様な価値観・考え方を持つ、多様な人々が描く回復の道筋を、承認していこうという考え方だ。これを「地域のレジリエンスを高めるために何が必要か」という観点で捉え直すと、次のようになるだろう。
——多様な回復の道筋が認められるような、多様な価値観を包摂する地域社会をつくることが、その地域社会のレジリエンスを高める。
キーワードは「多様性」だ。丹波教授も、「レジリエンスを表現する言い方として、よく『しなやかな強さ』という表現を使うが、その『しなやかさ』は多様なものを認めていくことから生まれる」と語る。
そして、丹波教授はレジリエンスを高めるために重要な要素として、他に「当事者性」と「受援力」を挙げる。当事者性とは、リスクをいかに“自分ごと化”できるかを意味する。また、受援力とは、他者からの援助を効果的に受け取る力、という意味だ。

「『当事者性』には二つの側面があって、一つは一人ひとりが“自分ごと化”の意識を高めることです。もう一つは、リスクを“自分ごと化”し、主体性を持ってリスクに対処するメンバーを増やしていくことです。そのとき、地域の中の人だけでなく、当事者としての認識を持ち、関わってくれる地域外の人を増やしていくという発想も大事だと思います。
そこで大事になってくるのが、『受援力』です。地域はとかく閉鎖的になりがちで、よそ者にとってはなかなか入りにくいところがあります。けれども、だんだん溶け込んでいくと地域の懐の豊かさみたいなものがわかってきて、その地域を愛しく思うようになるものです。それが地域外から当事者性を持って関わってくれる人を増やすチャンスになるわけで、外からの援助が入りやすくしておくことがとても大事なのです」
丹波教授によると、今、被災地は、新しい要素を迎え入れていこうとする動きが被災直後に比べて活発になっているという。外から入ってくる人やさまざまなリソースが、地域に多様性をもたらし、より新しいもの、より良いものを創り上げていく原動力にもなっているのだろう。
“自分ごと化”を経験した若者が、レジリエンスを高める芽となる
最後に、丹波教授の個人的なエピソードに触れておこう。丹波教授が立命館大学の災害復興支援室を通じ、学生と一緒になって何度となく福島に足を運んでいるのは、自身の学生時代の体験が影響しているのだという。
1995年の阪神・淡路大震災のとき、丹波教授は愛知県の大学の学生だった。周りの友人がボランティアで被災地に入っていく中、自身は一度も行かなかった。そのことは、後ろめたい思いとなって残った。その後、大学院生になって住宅の調査のために兵庫県の西宮市を訪れた際、問題の大きさを実感するとともに、“自分ごと化”するとはどういうことなのかを身をもって理解する。
2004年、助教授として福島大学に赴任すると、10月に新潟県中越地震が発生。隣県での被災に、迷わず学生たちに「支援に行こう」と呼び掛け、足を運んだ。そして、2011年の東日本大震災では、自身も被災者になった——。

「私の場合は、どこか“人生、巡り巡って”みたいなところがありますよね。でも、真面目な話、若い頃の経験は、その後の人生のどこかで必ず生かされていくものだと思っています。
若い世代の人たちがリスクを“自分ごと化”する経験をし、将来のリスクに対する想像力を働かせることは、その人自身にとって大きな意味を持つはずです。そして、当事者性を身に付けた若い一人ひとりが、これからの社会のレジリエンスを高めていく芽となってくれると思うのです」

丹波史紀
1973年愛知県生まれ。2004年3月から2017年3月まで福島大学行政政策学類准教授。2017年4月より立命館大学産業社会学部准教授。2020年4月より同教授。
専門は社会福祉学。生活保護やひとり親家庭の社会的自立などを研究。2011年の東日本大震災および原子力災害では、被災者支援とともにその実態調査などにも取り組む。福島県浪江町・双葉町の復興計画などの委員、大熊町の第2次復興検討委員会・委員長なども務める。