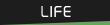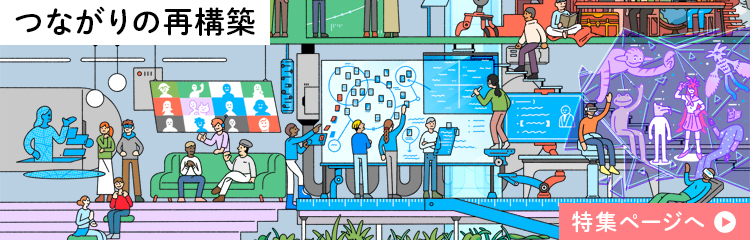子どもの貧困が社会問題となっている。特にひとり親家庭は、母親や父親の就労率が高いにもかかわらず貧困率は50%を超えているという。こうした構造的な問題の原因はどこにあるのか。求められる社会的な仕組みや解決策とは?
● 高い就労率にもかかわらず貧困が日本の特徴
● 固定化された性別役割分業が低賃金を招く
● パンデミックの影響を大きく受けたひとり親家庭
●生活困難層には必要なのは「ユニバーサルなサービス」
● ロールモデルの存在が子どもの未来を開く
「働いているのに貧困から抜け出せない」ひとり親家庭の実態
子どもの貧困の原因は、時代によって大きく変化する。たとえば、戦後間もなくは戦災孤児が社会問題化し、その後は子どもの遺棄や虐待が問題となってきた。子どもの貧困は、常に社会が抱える問題を映し出す鏡であったともいえる。
では、現在の子どもの貧困の実態は、どのように捉えられるのだろうか。これまで東北や近畿で就労支援を受けた母子家庭の調査や支援を実施してきた、立命館大学産業社会学部の丹波史紀教授に聞く。
「現在、大きな課題となっているのは、ひとり親家庭の貧困が子どもたちに与える影響です。日本のひとり親家庭の大きな特徴は、『働いていても貧困状態にある』ということです。日本ではシングルマザーの8割から9割近く、シングルファーザーでは9割以上が職を持って働くことができています。この割合は諸外国に比べると明らかに高いものです」(丹波教授、以下同じ)
時代に対応できない理由は、「性別役割分業」の名残り
「長らく日本では、『夫が働いて妻は専業主婦』という時代が続きました。こうした性別役割分業に基づく世帯から、共働き世帯が徐々に増え、近年では逆転しています。しかし、日本では長らく性別役割分業の固定化が続き、企業や社会もそれに合わせた形で、企業内福利や扶養手当など社会保障制度を男女の固定的な役割分業を前提にした仕組みで対応してきた経緯があります。
しかし、そのような仕組みを引きずった状態は、家族の多様な有り様や、ひとり親家庭が直面する困難に対応できていません。ひとり親が貧困に陥る大きな要因は、安定した生活が送れるような賃金体系になっていないことに尽きます。日本ではいまだに女性の賃金は男性の60〜70%であり、明らかな格差が残っています。
結婚や出産によって労働市場から一時的に退出していた女性が、離婚などによって改めて仕事を持とうとしても、パートタイムやアルバイト、派遣社員といったような不安定な就業形態しか選択肢がない。一方、いまだに待機児童の問題が解消されていないように、子育て環境も十分ではないために、母親が正社員で働きたいと考えても、子育てと仕事とのやりくりがつかず、派遣やパートタイムなど、自分で時間の都合がつけやすい仕事に就かざるを得ません。これが低賃金の構造を引きずる大きな要因です」
コロナ禍が浮き彫りにした子育て支援の課題と、「子育て参加」の違和感

そのような状況に追い打ちをかけたのが、新型コロナウィルス感染症によるパンデミックだ。非正規で働かざるを得ないことも多いひとり親の困難は、ますます大きくなっている。
「コロナ禍のように幅広い業界で休業が余儀なくされるような事態になると、ひとり親家庭、派遣や非正規で働く人たちなど、さまざまなハンデキャップや困難を抱えている層ほど、影響を受けやすくなります。昨年、学校の一斉休校が行われた際も、もっとも苦境に立たされたのは、テレワークや在宅ワークができない仕事に就いているひとり親家庭などでした」
子育てをしながらでも、安心して就労ができるような状態にすることが、子どもの貧困を解決していくことにつながる。そのためには、行政や地域が保育環境を整備することや、企業や働く現場の意識改革も必要だ。
「ダイバーシティや働き方改革などに対する意識の浸透によって、男性、女性に関係なく働ける環境を整えるという方向には進みつつあります。しかし、女性の社会参加という点で、日本はまだ世界で下から数えたほうが早いぐらいの状況です。結婚や出産などを機に、女性はリタイアせざるを得ない、仕事をセーブせざるを得ないというような状態に置かれやすい状況は変わっていません。
日本ではまだ、『男性が子育てに参加する』という言い方をしますが、これは非常に奇妙なのです。子育ては“参加”するものではなく、夫婦がお互いに責任をもってあたるものですから。このような視点から、性別役割分業の影響を弱めていく必要があるでしょう」
兵庫県明石市の子育て支援に見る「ユニバーサルなサービス」の必要性
不安定な就労状況におかれる女性や、ひとり親家庭への支援には、どのような視点が必要になるのか。コロナ禍における公的な支援で、丹波教授が注目している事例を聞いた。
「たとえばドイツでは、コロナ禍に対して、通常の休業補償が賃金の6割のところを8割にしたり、補償期間を1年から2年に延ばしたりといったように、既存の社会保障を充実させることで対応しています。
一方で日本の場合は、10万円の給付に、『困難な家庭のひとり親に対してはプラス5万円』など、支援は一時的で急場しのぎです。コロナ禍だけでなく、さまざまなリスクに対応できる社会保障の仕組みが十分でないことが、ドイツと日本との決定的な違いといえます。
そうした中で、注目を集めているのが兵庫県明石市の子育て支援です。同市では、子育て支援の施策によって人口がV字回復しているほどです。その施策の大きな特徴は、“ユニバーサルなサービスである”こと。貧困家庭の子どもだけを対象とするのではなく、所得や属性に関係なく明石市に住むすべての子どもが対象です。実は、サービス対象を絞り込まないことによって一番メリットを受けるのは、富裕層ではなく、生活が困難な層なのです」

財源問題などで、支援対象が絞られることは少なくない。しかし、その選別の過程でグレーゾーンの家庭が支援からこぼれ落ちるといった問題は常につきまとっている。
「すべての子どもや家庭を対象にするというユニバーサルな、あるいは普遍主義的な対応が、社会全体に効果を及ぼすわけですから、今後の社会的な政策は、こうした姿勢で充実させていくことが大切です」
子どもたちが「人生を変えるような第三者」に出会う機会を
子どもの貧困を、親の経済状況から考えてきたが、一方で子どもたち自身への支援としては何が必要なのだろうか。丹波教授は社会的な気運が大切で、ロールモデルが重要と訴える。
「地域の変化や社会的な気運が重要になってくると思います。たとえば、『子ども食堂』という取り組みが全国で進んでいて、子どもの貧困の問題にあたってきたNPOや団体などだけではなく、町内会や企業なども応援するようになっています。これはある意味でいい変化であり、子どもの貧困問題を社会全体で解決していこうという気運の表れだと思います。
アメリカなどの海外ではチャリティの文化、寄付の文化が根づいていて、企業の経営者は社会的な責任として社会問題の解決に取り組むことが常識になっています。しかし、日本はそれが十分とはいえない。国や自治体、企業だけでなく、社会全体で解決していくという気運を醸成しないと、制度を改善しても実のあるものにはならないでしょう。
また、社会全体で子どもの支援にあたる上で大事なことは、親や学校の先生ではなく、『魅力的な第三者のロールモデル』がいることです。大学生でもいいかもしれないし、地域の憧れの存在のような人でもいいでしょう。人生を変えてくれるような第三者に出会えるかどうかは大切なことです。先ほどの子ども食堂でも、そこで安心して信頼できる大人に出会えることが大切なのです。その経験は、子どもたちのその後の人生で大きな花を咲かせることにつながると考えています」

丹波史紀
1973年愛知県生まれ。2004年3月から2017年3月まで福島大学行政政策学類准教授。2017年4月より立命館大学産業社会学部准教授。2020年4月より同教授。
専門は社会福祉学。生活保護やひとり親家庭の社会的自立などを研究。2011年の東日本大震災および原子力災害では、被災者支援とともにその実態調査などにも取り組む。福島県浪江町・双葉町の復興計画などの委員、大熊町の第2次復興検討委員会・委員長なども務める。