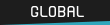世界各地で右派的な政治運動が勢いを増す中、日本でも「反グローバル」「伝統回帰」を掲げる新しい潮流が台頭している。参政党などの動きは、一過性のブームなのか、それとも社会構造の変化を映す兆しなのか。ナショナリズム研究を専門とする立命館大学国際関係学部のナサニエルM.スミス准教授は、ネットを介した草の根動員や若者の意識変化に注目する。日本の右傾化現象を、世界の文脈の中でどう読み解くべきか――その考察は、現代社会の「つながり」と「分断」の本質を問い直すものだ。
● 参政党現象が示す新しい政治参加のかたち
● 「反グローバル」日本と欧米の構造の違い
● トランプ再選と民主主義の“制度と精神”
● 「反グローバル」は成立しない
ネット×草の根が広げた“曖昧な共感” 参政党現象が映すもの
2025年の参議院選挙で注目を集めたのが、いわゆる「反グローバル」「伝統回帰」を掲げる新興勢力の動きだ。なかでも参政党は、動画配信やSNSを活用して若者や主婦層を巻き込み、草の根的な支持を拡大させた。ポスターの色づかい、キャッチコピー、YouTubeのサムネイルに至るまで、マーケティングの細部にまで設計された“参加型の政治”を演出した点が特徴的だ。
「最初に感じたのは、ネットの役割が政治において一段と増したということです。特定の主張や政策ではなく、『自分たちで何かを変えたい』という空気感に訴えた。反ワクチンや反マスクといった論点が“入口”になり、そこから緩やかな共感の輪を広げたことが大きかったと考えています」(ナサニエルM.スミス准教授、以下同じ)
この「入口の多様さ」こそが、従来の右派政党とは異なる点だ。主張の細部はあえて曖昧に保ち、支持者がそれぞれの関心や不満を投影できる“余白”を残した。そこに、デジタル時代における拡散力が重なった。
「参政党は、『曖昧さ』を上手に使った政党です。特定のイデオロギーに強く結びつけず、“とりあえず賛成してみよう”という参加のハードルを下げた。それが新しいタイプの草の根運動につながったのだと思います。
政治的な主張というよりも、SNS上のコミュニティに“共感”で参加する。参政党の伸長は、政治への“参加のかたち”が変わりつつある現代社会を映しているものともいえます。
同時に、その曖昧さは、現実の課題解決や合意形成を難しくする側面も持ちます。こうした“柔らかい結束”が次の選挙でどう作用するか、中期的に存続しうるかを見極める必要があるでしょう」
SNSを通じて集まった人々は、強い信念よりも“気分”でつながっている面もある。これが政治的エネルギーとして成熟するのか、それとも消費されて終わるのかに注目する必要がありそうだ。
世界の右派台頭と日本――共通する“技術”、異なる土壌
欧米では、トランプ前大統領の再浮上やフランス国民連合(RN)、ドイツのAfDなど、右派勢力の台頭が続いている。グローバル化が進むほどに、ナショナリズムが強まる――そんな逆説的な動きが、各国で同時多発的に起きている。
日本の参政党や保守的な新勢力も、その延長線上にあるように見えるが、スミス准教授は「見た目の共通性に惑わされてはいけない」と指摘する。
「欧米と日本では、“右派化のエンジン”が違います。アメリカやヨーロッパでは、移民や宗教、階級といった明確な対立構造が政治の燃料になります。しかし日本では、移民が少なくても排外的な語りが支持を集める。つまり、実際の分断よりも“想像上の分断”が政治を動かしているのです」
その“想像上の分断”を拡大させているのが、デジタル技術の存在だ。SNSや動画配信など、個人が情報発信の主体になれる仕組みが、政治のプラットフォームを根底から変えた。
「日本においては、思想より“技術”の側から政治が変化していると見ています。
技術的な側面では、日本も世界の右派運動と共通しています。個人がメディアとして発信し、資金を集め、人を動かす。従来の政党組織を経由せずに動員できる仕組みが整った。それが“草の根の右派”を支える技術的な基盤になっています。
ただし、政治の構造自体は欧米と大きく異なります。欧米の右派が既存のエリート支配への反発から生まれたのに対し、日本では、長年にわたって「保守」を包括してきた自民党の求心力が緩やかに低下してきました。その結果、既存の保守からこぼれ落ちた層が、自らの立ち位置を再定義しようと動き始めたと見るべきでしょう」
日本においては、保守が長く“与党”と同義語だったといえる。しかし、近年はその中身が多層化しているのはご存じの通りだ。
「一枚岩ではなくなった保守層の中で、より純化された“新しい保守”を名乗る動きが現れた。これは一時的な現象ではなく、政治文化の再編成と見るべきでしょう。欧米に比べれば、日本の右派的言説は穏やかで、既存制度の枠内に収まっています。それでも、社会の周縁に潜む不安や孤立が新たな言葉を得たとき、その動きは再び大きなうねりになる可能性を秘めています」
トランプ再選が突きつけた“民主主義の脆さ”
2025年、トランプ大統領が再びホワイトハウスに戻った。そして、アメリカ社会は分断の修復どころか、むしろ“選挙で選ばれた分断”という新たな段階に入っている。この出来事は何を意味するのか。スミス准教授は「民主主義の“手続き”と“精神”の乖離が深まっている」と語る。
「トランプ再選は、単に右派の勝利というより、民主主義の形式が機能しながらも、内容が失われつつあることを象徴しています。選挙は公正に行われ、制度は守られている。けれど、人々の間では“相手を敵とみなす文化”が定着し、妥協や対話が成立しにくくなっている。それが今のアメリカ社会の最大の危機です」
かつて民主主義を支えていたのは「相互の信頼」と「常識への敬意」だった。だが、SNSを通じて拡散される感情的な情報が、共通の現実を侵食している。スミス准教授は、こうした“構造的な不信”が他国にも波及することを懸念する。
「民主主義は制度だけで自動的に機能するものではありません。“違う意見があっても同じ社会に属している”という感覚が失われたとき、制度は形だけ残る。場合によっては本来の意義そのものが破壊される。その意味で、トランプ再選はアメリカの問題であると同時に、世界の民主主義に対する警鐘なのです」
極端な主張が拡散しやすく、複雑な現実が単純化される時代。日本の政治もまた、こうした「構造的な脆さ」と無縁ではないだろう。
現在の世界で“反グローバル”は成立しない
いまや「反グローバル」という言葉は、政治的立場を示すだけでなく、生活不安の代名詞としても使われるようになっている。物価上昇、賃金停滞、観光の混雑、地域格差――。それらをひとまとめに「グローバル化のせい」と語る風潮もみられるが、スミス准教授はそこに危うさを見る。
「グローバル化は“外から押し寄せるもの”ではなく、すでに世界の前提そのものです。日本の経済も文化も、国際的なつながりの上に成り立っている。そしてそれは世界中のどの国も同じです。
ですから、“反グローバル”というスローガンが現実的に意味するのは、『変化の速度に追いつけない社会の戸惑い』であり、言い換えれば『変化による格差に対する不満の表出』なのだと思います。グローバル化を拒む言説の一部には、陰謀論的な語りも混じっていますよね。その背景にあるのは、複雑な現実を単純化し、原因を『誰かの意図』に求める心理です。それが社会の分断を深め、冷静な議論を妨げています。
言い換えれば、陰謀論は“理解の近道”なんです。現実の仕組みを学ぶよりも、誰かのせいにしたほうが簡単だからです。しかし、そうした語りが広がると、問題を解決するための知恵や対話の場が失われてしまいます」
反グローバルという言葉が指し示すのは、世界と切れる願望ではなく、変化の中で「どうつながり直すか」という問いなのかもしれない。
2026年衆院選はどうなる?
2025年10月、自民党総裁選で高市早苗氏が選出され、日本初の女性総理大臣が誕生した。高市内閣の発足以降、政権支持率は急回復し、長期低迷していた自民党の求心力が一気に戻りつつある。国内外で右派的潮流が注目を集めるなか、女性リーダーはいかに舵取りをしていくのか。2026年2月には衆議院解散に伴う総選挙が行われる公算が大きくなっているが、その影響は大きな焦点となりそうだ。
「個人的な印象にすぎませんが、現在、高市政権が目指している政治は、『リードできる日本』を想像させるものではなく、残念ながら『衰退を恐れている国家』の振る舞いのように感じます。
安倍政権でも根本的に右派的な政策がかなり多かった印象です。一方、安倍総理がイメージしていた日本像は、まだ世界を動かせる、自信のある日本国だったといえるでしょう。現在の観光ブーム、Cool Japan現象、留学生の増加と教育の国際化、労働力の導入の名目による社会多様化など、それぞれの現象の基盤にあったのは、『キャパシティーある日本』を打ち出す政策でした。少子高齢化と向き合うために、コロナ前までの保守陣営のスタンスはむしろ器が大きかったと言えます。
農業やその他の産業は特に労働力のニーズが高く、円安で『出稼ぎの場』として魅力が薄れている日本では、『反グローバル』的な政策が実現すると移民にとって暮らしにくい社会になってしまう。労働の担い手を育成する力が失われることは、日本人にとって大きなデメリットにもなると思います」
反グローバル、伝統回帰、ナショナリズム──。近年の政治をめぐる言葉は刺激的だが、スミス准教授の分析が示すのは、それらが必ずしも明確な思想や将来像を伴っているわけではないという現実だ。多くの場合、人々が抱えているのはグローバル化への拒否感ではなく、変化のスピードに対する不安や、生活実感とのズレへの戸惑いである。政治的スローガンは、その感情を束ねる「仮の答え」として機能しているにすぎない。
「反グローバル」という言葉の背後に、私たちは何を恐れ、何を守ろうとしているのか。その問いを自ら引き受けることが、いま求められている。

SMITH, Nathaniel
立命館大学国際関係学部・大学院国際関係研究科 准教授。PhD, Anthropology (Yale University)。
平成後期以降の極右政治運動に関する調査・研究を文化人類学の観点から行う。ナショナリズム現象を解明するプロジェクトや、多様化する日本の都市生活を考察するプロジェクトに取り組む。
2025年からは、国際関係学部 副学部長として、アメリカン大学と立命館大学が連携して展開しているジョイント・ディグリー・プログラムを担当。